サスタビの代表と、旅やサステナビリティについて考えるコーナー。今回は、「旅先にプラスの影響を与える旅ってどんな旅?」について考えてみました。議論が進む中で、社会における多様性の重要性についても考えています。ぜひご一読ください。
旅先にプラスの影響を与える方法とは
行方:今日は「サステナブルな旅って何だろう」ということについて、ディスカッションしたいと思います。サステナブルな旅って、長井さんにとってどんな旅ですか?
長井:私の答えとしては、「旅先に対してポジティブな影響がある」というのが、サステナブルの旅の要素の一つかと思います。
行方:ポジティブというのは、旅先の地域に何かプラスの影響を与えるということですか?
長井:そうですね。旅人が楽しいだけではなく、「旅人を受け入れた人や土地に、何かいいことがある」、それがポジティブだと思います。
行方:「ポジティブになる」というのは、どんなイメージですか?サステナブルな旅をすると、どんな風に「地域にプラスになる旅」ができるんでしょうか。

長井:いくつかのパターンがあると思います。例えば、その土地ならではの文化や伝統工芸品に触れたり、実際に購入したり、鑑賞したりというのが一つです。他にも、その土地ならではのものを食べる「地産地消」や、街や自然を綺麗にするような活動をすることなども、旅におけるポジティブに繋がると思います。
行方:なるほど。今回は、旅先で文化や伝統に触れることがなぜ持続可能な社会を作ることに繋がるか、議論したいです。長井さんは、どういう理由があると思いますか?
長井:文化や伝統は、土地によって違いがあります。よそからやって来た旅人からすると、その違いを知るだけで楽しく、旅の思い出になりますよね。また、その文化を継承している人に興味を持つことも、ポジティブな要素ではないでしょうか。
文化の担い手からすると、自分の暮らす土地の文化を旅人に楽しんでもらったり、作ったものを購入してもらったりということが、文化に取り組む意義に繋がっていると思います。また、そこで発生する金銭が担い手の生活を支える面もあるのではないでしょうか。
行方:たしかに、地元の伝統工芸品などを買ってもらって、それが金銭的なメリットになるのはありますね。その前の、「文化を楽しんでもらう」の部分について、もう少し教えてもらえますか?
長井:外から来た人に見てもらう、楽しんでもらうこと自体が、文化の担い手にとってモチベーションになるのではないでしょうか。より前向きに取り組むことによって、自分たちの伝統を長く守っていくことに繋がるのかなと。
多様性がもたらす持続可能な社会
行方:旅人が地域の文化を楽しむことが、地域にポジティブな影響を与えることがわかりました。サスタビでは「旅を通じて持続可能な社会をつくる」というコンセプトがありますが、社会全体にとって何かいいことはあるんでしょうか。
長井:多様性の促進という面があると思います。土地の文化が引き継がれず場所による違いがなくなると、全国的な文化の画一化が進んでしまうと思います。そうなると、自分と違う考え方や感じ方を知ったり、見たことのないものを発見したりといった機会がどんどん失われます。
そうなると、一人ひとりの視野がすごく狭くなってきてしまうのではないでしょうか。いずれは「自分が考えることが全て」だと思ってしまい、違いを受け入れる寛容性が失われていくと思います。日本全国で土地の伝統を守ることは、多様性を保つことに繋がってるのかなと思います。

行方:確かに、多様性に繋がりそうですね。根本的な疑問ですが、持続可能な社会を作るためには多様性やインクルージョンが重要だと言われますが、それはなぜなのでしょうか。
長井:やはり、寛容性がポイントになるのではないでしょうか。人々が寛容になり、色々な形のものが同時に存在することが、社会の継続に繋がると思います。
行方:何事も、一つの形しかなければそれだけが正しいと思ってしまいますね。違いがあるからこそ、それを受け入れて平和にやっていく取り組みが生まれます。寛容性が失われると、自分と違うものを敵とみなして攻撃してしまいそうです。
長井:そうなると、持続可能な社会とはなかなか言えないんじゃないかなと。
行方:また、環境や社会に適応しながら変化していくことが持続可能を実現するポイントだと思いますが、宇宙全体でも変化が起きていますね。そういう世界で暮らす中で、多様性という切り口は非常に大切な要素になると思いました。
長井:そうですね。人が100人いれば全員違いますし、地域も文化も違います。違うものは、違うままでいいんだろうと。一律にしてしまうと変化が生まれません。組織や社会を運営する上ではルール化することが楽で便利ですが、伝統や文化はばらつきがあるものです。
行方:環境一つとっても、北極があれば熱帯雨林もあると。それによって根付く文化も違うのに、無理に一律にしていくことは難しいです。もし一律になっても、変化が生まれないのは大きなデメリットですね。

長井:今日は、旅をきっかけに多様性の重要性について改めて考えることができました。旅に出ることでいつもとは違うものを見て、色んな可能性に気づくことができますね。今の日本はタイパとかコスパという言葉もあり、いかに短い時間で何かを成し遂げるかに重きが置かれていますが、多様性はその逆にあると思います。種類が多ければ多いほど面倒くさいし、時間がかかるものです。
行方:それをいらないと切り捨てるのか、それとも違いがあることによるメリットを取るのかで、社会の形が変わると思います。ただ、一律化を進めてもどこかで多様性は生まれるのではとも思います。
例えばマクドナルドは世界中で同じ味が食べられるように一律化を進めましたが、結局は国ごとのメニューを作って、土地にあわせた多様化が生まれましたよね。一つにまとまっても、その後にバラバラになっていくというバランスが大切なのかもしれません。こういった現象はグローカリゼーションと呼ばれ、様々な研究がなされています。*1
旅はもちろん、社会全体において、多様性は本質的に大切なのだろうと思いました。今日はありがとうございました。
*1参考文献
・前川啓治(2004)『グローカリゼーションの人類学:国際文化・開発・移民』新曜社
・阿良田麻里子編(2017)『文化を食べる文化を飲む : グローカル化する世界の食とビジネス 』ドメス出版。




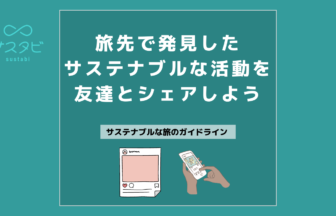
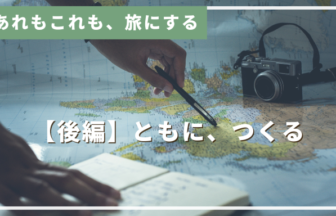

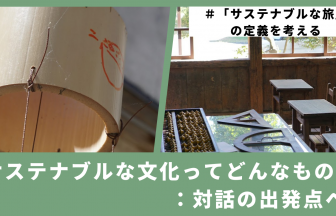
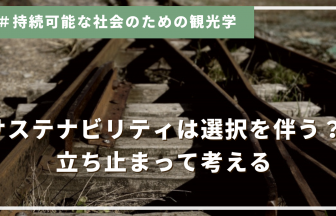
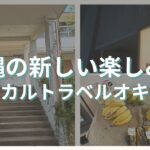


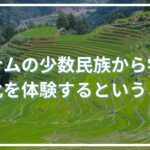




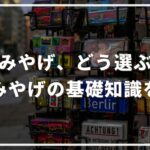
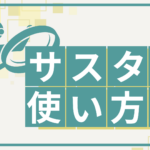



この記事へのコメントはありません。