観光と「本物らしさ」
みなさんは観光に行くとき、何を重視しますか?
食や著名な景観、アトラクションなどさまざまな観光目的があると思いますが、なんとなく「その地域のもの」を食べたり見たりしたいと思う方がほとんどだと思います。その地域で採れた食、その地域でつくられたもの、その地域の伝統、その地域の文化などなど。せっかく観光地に来たのに、いつでも食べられるようなチェーン店に入るのはもったいないと思いますよね。「ご当地」「その地域らしさ」は、観光では非常に重視されています。
観光研究の有名な概念に、「真正性」というものがあります。英語ではオーセンティシティ(authenticity)といいます。直訳すれば「本物らしさ」ですね。ディーン・マキァーネルという方は、観光において人びとは「真正性」を追求するのだと指摘しました。
日常生活や労働で疲れ、自分を見失ってしまったとき、観光に出て非日常の時間を過ごし、そのなかで「本物」の文化や自然に出会うことで失った自分の実存を取り戻す。そのようなメカニズムとして観光を捉えたのです。
この「真正性」は、先ほど述べた「地域性」「その地域らしさ」の話題と深く結びついています。いうなれば、いま私たちにとっての「真正性のある観光の経験」の大部分は、「その地域のものを食べたり見たり楽しんだりすること」となっているということですね。

どこからどこまでが「その地域のもの」?
観光の「お土産」と「来歴」
観光と「その地域らしさ」の関係を考えるうえで興味深いのが、「お土産」です。
多くの方が、観光に行ったら自分や友人などのためにお土産を買って帰ると思います。それも、「その地域らしいもの」を。お土産を選ぶことが好きという方は多そうですね。
観光地で売られているお土産は実に多様です。パッケージに観光地の有名な場所や地名が書かれた個包装の箱菓子は友人に配りやすいし、「私がその場所に行ってきたこと」を簡単に他者に伝えることができます。「ご当地キティ」「I Love ○○(地名)Tシャツ」などの商品もよく目にしますね。その地域の伝統的な工芸品や産品、地酒なども販売されています。
そうしたお土産物を選ぶとき、当然、その産地をみなさんも確認すると思います。パッケージの裏側に記載されている生産者名や販売者名をよく見ると、実はそのお土産がその地域ではなく別の場所で生産されていた事実に気づくこともあるでしょう。そのとき感じる「ガッカリ」は、そのお土産が「地域のもの」ではなかったことに対する落胆にほかなりません。それは、「地域のもの」という「真正性」が損なわれたことへのガッカリだといえます。

しかしながらお土産物と真正性との関係は、もっともっと複雑です。たとえば浅草を事例としたとある研究の、とても興味深い指摘をみてみましょう(鈴木 2023)。
東京・浅草の仲見世通り。観光客で賑わう著名な観光地です。そこで売られているお土産には、たとえば「おいもパイ」、「人形焼き」「富士山キーホルダー」「浮世絵柄のシャツ」「キャラクター商品」などがあります。

しかしそれらのお土産が「その土地のもの」「その土地の産物」であるかといえば、実はそうではありません。外国人観光客向けに売られている「富士山キーホルダー」や「浮世絵柄のシャツ」は日本の名産と言えるでしょうか?生産も、そのほとんどが海外工場で安く大量生産され日本に送られてきたものです。「キャラクター商品」もまた、ライセンス企業が海外工場で生産したものがほとんどでしょう。
「人形焼き」はどうでしょう。その場で焼きたてが売られており、「浅草らしさ」がありそうにみえます。しかしこれも原材料までたどれば、輸入品も含まれています。「おいもパイ」は「いも羊羹」の老舗などで売られており歴史や伝統を感じますが、「パイ」はそもそも西洋由来ですね。
このように、お土産物の「来歴」を原材料レベルまでたどってみれば、浅草で売られているお土産物の多くは「完全にその土地のもの」とは言えず、「真正性」の問題として厳しく判定するならば「ニセモノ」になってしまいます。

「お土産物の旅」
そこから鈴木は、「おみやげ=その土地の産物」という図式では、観光の場で売られているお土産のことを適切に理解することはできないと指摘し、お土産と真正性との複雑な関係性を捉えていく必要性を述べています。
たとえば「江の島みやげ」として海外からも人気を博している「貝細工」は、かつて海外や、江の島以外の全国国内から貝を輸入して始まったものです。それを現在江の島を訪れた日本人や外国人が買っていくのですから、現象としては「逆輸入」といえますね。

「江の島貝細工ものがたり ~小さな島に世界的な伝統産業があった~」https://san-tatsu.jp/articles/179965/
鈴木が例に挙げる「マトリョーシカ」は特筆すべきものです(鈴木 2023)。
浅草では、忍者や着物姿のマトリョーシカが売られています。マトリョーシカといえば、「ロシアの民芸品」として知られていますね。入れ子細工の人形で、スカーフを巻いた女性の図柄が描かれているものが一般的です。浅草で売られている忍者や着物のマトリョーシカは、中国製だそうです。

「Nittax.inc」https://nittax.jp/item/mascot/
そして興味深いのはここからです。
マトリョーシカは、実はそのルーツは神奈川県・箱根だとする説が有力視されています(ゴロジャーニナ 2013)。「フクルマ」という、当時箱根で作られていた七福神の入れ子人形が、19世紀後半に子供向け玩具製作のために世界中の民芸品を収集していたロシアの旋盤工ズビョーズトチキンと画家のマリューチンの手に渡り、彼らによって現在のマトリョーシカの原型が製作されたとする説です。
この「マトリョーシカ箱根起源説」をもとにすれば、浅草で売られているマトリョーシカはきわめて複雑な性格を有しています。以下に整理してみましょう。浅草で売られているのは……
外国人向けに売られている、日本らしい(忍者・着物)絵の施された、もともとは箱根が起源とされる、だけれども中国製の、ロシア民芸品。
ということになるのです。「真正性」はいったいどこにあるのでしょうか?浅草のマトリョーシカはホンモノ?ニセモノ? そうした尺度で測ることがもはや適切ではないように思えてきますね。
ルーツを知ること
ホンモノか、それともニセモノかはともかくとして、こうした「ルーツ」に意識を向け、観光地に売られているものや表現されているものを多角的に捉えてみることもひとつの旅の魅力かもしれません。
ルーツを知ることは、「今現在自分の目の前に広がっている景色が、どのような物語を経て今に至っているのか」を知ること、すなわち観光地の「物語」を知ることだと言えます。これは、観光地の歴史や文化を学ぶことの一環ですね。
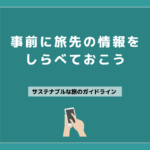
そうしてルーツを知ることで、もしかしたら「ガッカリ」してしまうこともあるかもしれませんが、普通では知り得なかった奥深い地域の物語や歴史に触れ、その旅をいっそう魅力的なものにしてくれる可能性もあるでしょう。
参考文献
- 鈴木涼太郎(2023)「おみやげ」『移動時代のツーリズム』ナカニシヤ出版、122-129。
- ゴロジャーニナ、G.(2013)『ロシアのマトリョーシカ』スペースシャワーブックス。
サスタビ外部アドバイザー担当。北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院 専任講師。立教大学大学院観光学研究科 博士課程後期課程修了。博士(観光学)。専門は文化人類学、観光研究、モビリティ研究。北海道札幌市出身。
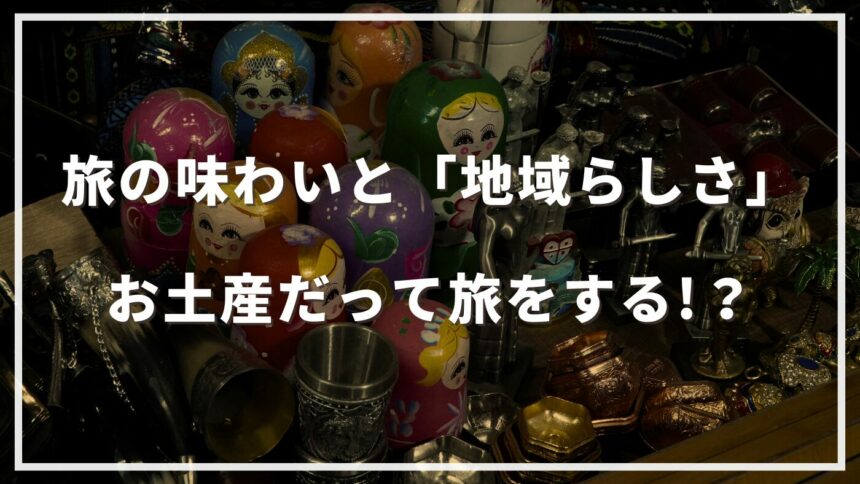

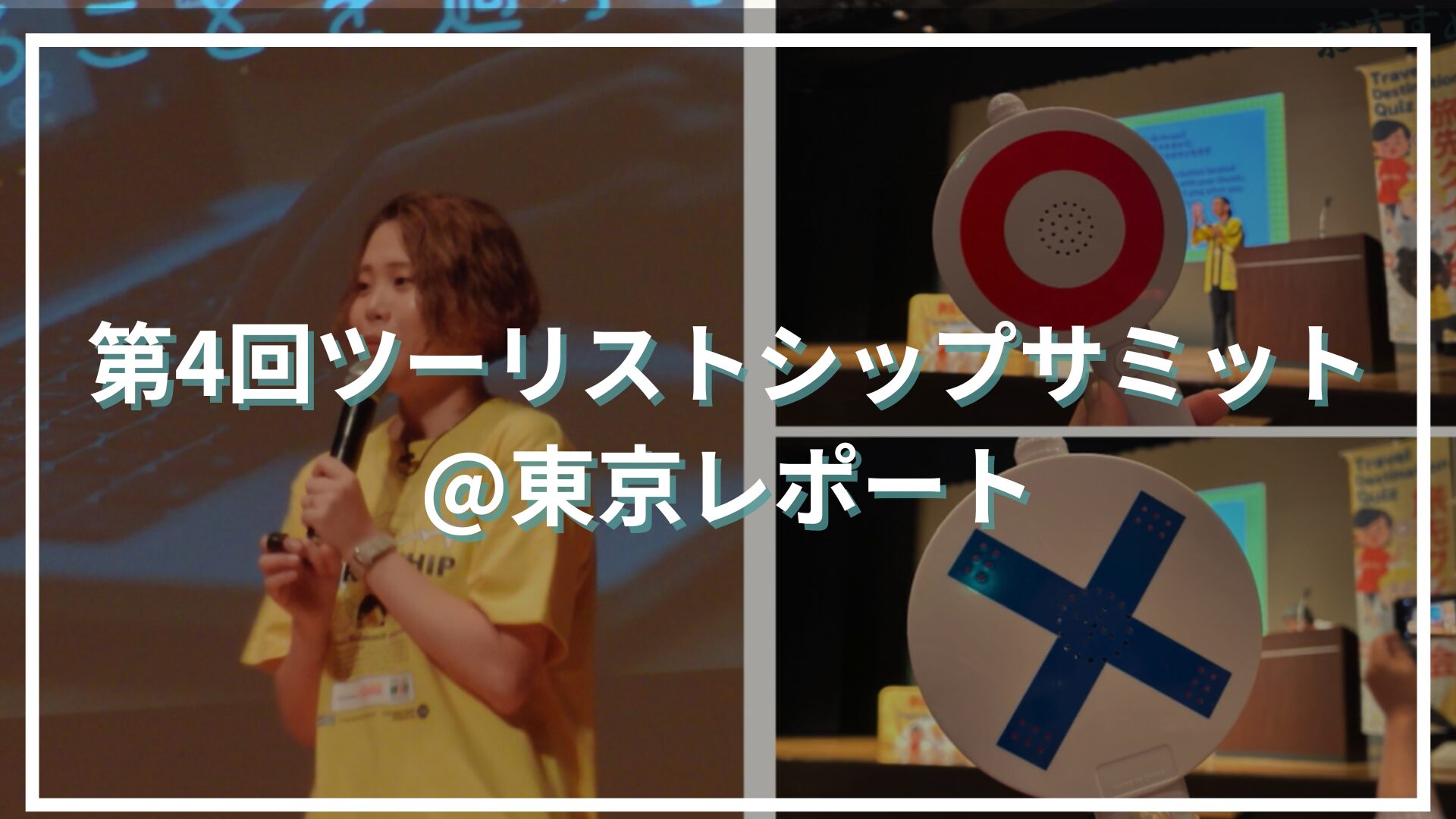
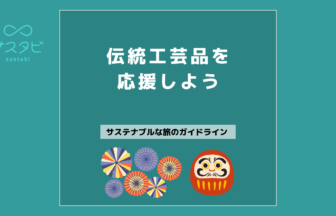

-336x216.jpg)

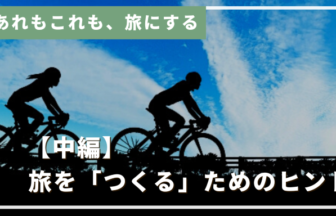

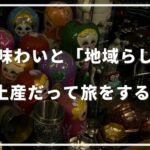
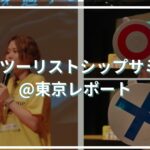

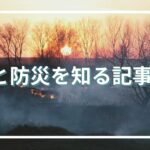

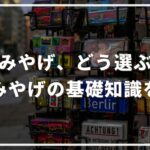

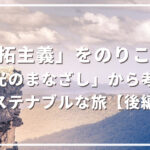





この記事へのコメントはありません。