「オフグリッド」
オフグリッドという言葉をご存じでしょうか。
これは、電力やガスを供給するために電力会社が張り巡らせたエネルギー供給網(グリッド)から切り離され、ソーラーパネルや風力発電、水力発電などによってエネルギーを自給自足しながら生活するための住居や町のことを指す言葉です(Vannini 2014)。よくある間違いとして、電力やガスの一切を使用しない生活のことをオフグリッドと呼称したり、近年では電力会社が斡旋する太陽光発電システムの販売においてこの言葉が使用されたりする例も散見されますが、それらは厳密な意味でのオフグリッドとは意味が異なります。既存のグリッド、すなわち外部から供給されるエネルギーのインフラストラクチャーに依存した生活から脱する(off)こと、そしてそのうえで自らの生活の仕方を自給的に再構築することが鍵となります。

「場所とつながる」ためのオフグリッド
電気や天然ガスの送電網から自らの住居や生活地域を切り離し、オフグリッドな状況でサステナブルな生活を試みる人びとが、カナダをはじめ世界各地で存在します。
カナダにおいて都市のいわゆる「現代文明」から抜け出し、オフグリッドな生活を試みようとする人びとを調査した社会学者フィリップ・ヴァニーニ(Philip Vannini)の著作『Off the Grid』(2014)があります。その本では、オフグリッドで創意工夫や試行錯誤を繰り返しながら、「自らと周囲の環境との関係性を再構築」(p.18)していこうとする人びとの実践が描き出されています。
「オフグリッダー(off-gridders:オフグリッドな生活をする人)たちは場所を占有するのではなく、場所とつながることを目的とした居住の形態」(p.53)をとる。
電力網という近代的なインフラストラクチャーのネットワークから「離脱」することが、「場所とつながる」ことに結びつくという視点はとても興味深いものがあります。
電気があるという当たり前
いま、自宅でこの記事を読んでいるあなたの家には、コンセントがあるはずです。そこにプラグを指すだけで、パソコンやテレビ、冷蔵庫、電気ケトルなどあらゆる電化製品を使用することができます。道具によっては、つねに「挿しっぱなし」のものも少なくありません。「コンセントに指すだけで道具が使える」という状況に私たちは慣れきっており、その当たり前の状況を意識したり、疑いを持ったりすることはほとんどありません――地震や台風などの災害によって停電になるその時までは。

自然やエネルギーへの想像力
電力は私たちの生活を根本的に支えており、ひとたびそれが途切れれば、私たちは何もできなくなってしまうと言っても過言ではありません。ガスや水道も同様です。にもかかわらず、私たちは、自分が使用している電力やガスや水がどこでつくられ、どのようにして運ばれてきたものなのかを知らずに生活しています。電力会社等によって張り巡らされたエネルギー網のインフラストラクチャー(ネットワーク)は、電気や水道について生活のなかで心配する必要が全くないほど私たちを覆っているのであり、そのことが翻って、私たちと身近な自然環境やエネルギーとの直接的な結びつきを見えにくくさせています。エネルギーを作りだし供給するためにどれほどの資源が使用されているのかなど、想像すらしないかもしれません。
そうしてエネルギーについての想像力が不要な生活をしていると、身の回りの自然環境やエネルギーについて意識する機会もどんどん損なわれていきます。オフグリッドな生活における「場所とつながること」とは、そのようにして失われた自然環境との関係性についての想像力を取り戻そうとすることにほかなりません。

自然との関係性の回復にむけて
自分が使用するエネルギーが誰によって、どのようにして、いつ作られ、いかにして自宅まで運ばれているのかを意識し「見える化」するための契機として、オフグリッドの生活を捉えることができます。ソーラーパネルを使用して自然のリズムに応じた量の電力を作り出したり、川の流れを利用して水力発電をしたりと、自分の身体と知覚と想像力が届く範囲のなかでエネルギーを作り出すと同時に、そのエネルギーが賄うことのできる規模の生活を再構築しようとする試みです。
それは身近な自然環境との身体的な結びつきを回復しようとすることでもあります。その日の天候や季節に応じてエネルギーの量は変化しますし、そのエネルギー量の変化に応じて生活も変化させていかなければなりません。自分の生活と自然環境のリズムが重なり合っていくということですね。自らの生活のあり方を不変にするために周囲の自然環境をコントロールしようとする近代的な思考を問い直し、自然環境の変化に自らの生活をあわせていこうとする生き方や考え方を知ろうとする試みとして、オフグリッドはサステナブルな社会の想像のうえで示唆に富みます。
もちろん急に山奥に引っ越しし自給自足生活にシフトしたりすることは難しいですが、キャンプや自然体験アクティビティのなかで、エネルギーや自然との向き合い方を考え直してみることはできるはずです(単に自然を「消費」するようなレジャーが多いことも事実ですが)。また以前「食のトレーサビリティ」に関して紹介した記事も、自然との関係性を再考するという点で共通点があるかもしれません。ぜひこちらもご参照ください。

観光/旅における食 美味しい食を味わうことは、旅/観光のひとつの醍醐味ですよね。地産の食材やお酒を求めて地域に旅立つ人も多い事でしょう。今回の記事では、「食」に注目して、サステナブルな旅との関係を考えてみたいと思います。 知っているようで知らなかったような、「食×サステナブル」をめぐる基礎知...

すべての「食べる」人が対象の旅 皆さんは食べることが好きですか? 旅行に行ったら、ご当地グルメや地域の美味しいものに舌鼓を打つことが何よりも楽しみ、という方も沢山いらっしゃるのはず。 では、そうした料理や食材は、どこで、誰が、どんな風に作り、どんな想いが込められているのか、考え...

食との向き合い方を省みる 前回の記事(「食とサステナブルに向き合うために知っておきたい基礎知識」)では、食の「トレーサビリティ」についてご紹介しました。 私たちの食べ物が辿ってきたプロセス――食の生産から、流通、そして廃棄まで――が、どれだけ「見える化」されているかを示す「トレーサビ...

わかってるつもりでいた「命をいただく」こと みなさん、今日お肉を食べましたか?牛肉、豚肉、鶏肉、それともお魚でしたか? 私たちが普段食べている肉や卵、魚に野菜はすべて、もとは生きていた命。だからこそ、それを食べるときに私たちは手を合わせ「いただきます」という言葉を口にします。しかし「命をいただく」...
また、いわゆる「インフラツーリズム」に参加してみることも、オフグリッドと近しい発見のチャンスだと思われます。発電所やダムを見学したり、ゴミの処理場を見に行ったりすることなどですね。私たちの生活を支えているインフラストラクチャーについて知ること、エネルギーや食やゴミや道具の「トレーサビリティ」、すなわちどこから来てどこへ行くのかという行く末を「見える化」することも、自然との関係性を再考する手段です。こちらも参考記事を紹介します。

インフラストラクチャーとツーリズム 橋やダム、発電施設など、私たちの日々の生活や移動、エネルギー供給などを下支えしているインフラストラクチャー(以下、インフラ)が観光資源となるような旅/観光のことを、「インフラツーリズム」と呼びます。 今回の記事では、このインフラツーリズムを切り口にして、私...

生活や環境を支えている仕組みを学ぶ、インフラツーリズム 前編では、私たちの行動や移動を可能にしてくれている「インフラストラクチャー」の特徴について整理をしました。インフラは私たちにとってあまりにありふれている存在であるがゆえに、たとえば「この水はどこから来ているのだろう」「この電気はどうやって作ら...

石坂産業のゴミから始めるイノベーション https://sustabi.com/service/5987/ 埼玉県三芳町にある、おそらく日本でもっとも有名な産業廃棄物中間処理業者、石坂産業をご存じですか? 一般的には「きつい」「きたない」「危険」の3Kといわれるように、あまり良いイメージを持たれ...
サスタビ外部アドバイザー担当。北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院 専任講師。立教大学大学院観光学研究科 博士課程後期課程修了。博士(観光学)。専門は文化人類学、観光研究、モビリティ研究。北海道札幌市出身。
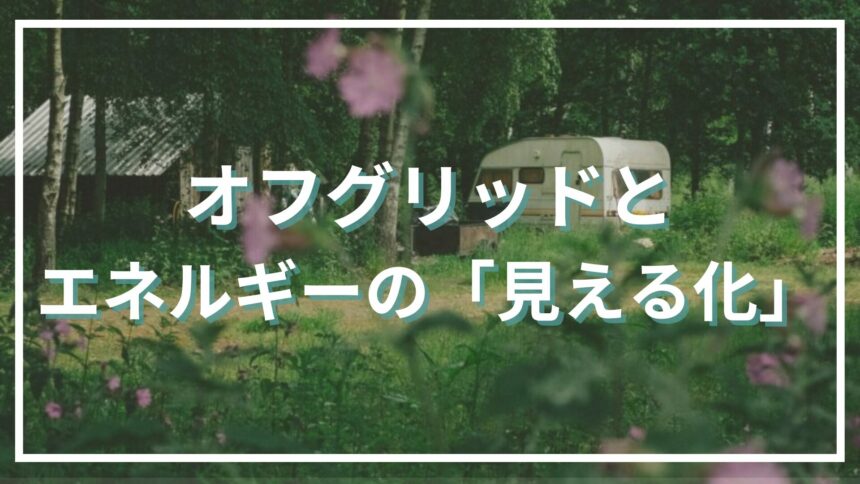
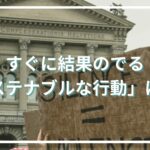

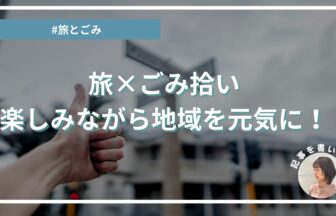





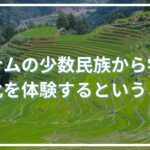


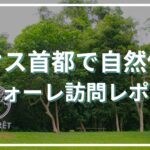

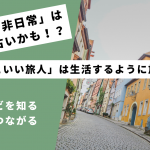



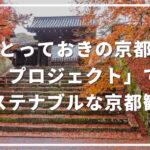



この記事へのコメントはありません。