サスタビ始動から3年。サステナブルツーリズムの在り方やこれから向かう先についてメンバー対談を行いました。
「旅の効用」やSNS時代の旅の仕方のヒントなど、旅がより豊かになるヒントが多く飛び出した回となりました!
メンバープロフィール
行方一正:
株式会社ピーストラベルプロジェクト代表/元HIS代表取締役専務。世界の相互理解と世界平和に繋がる事業への投資や支援。その他社外役員等を務める
岡村龍弥:
合同会社Guild 代表/サスタビ総合プロデューサー。「自分らしく生きる人を増やす」を理念に、旅・地域・教育を軸に活動中。
宮野かがり:
フリーライター・エシカル・コンシェルジュ/サスタビライター、コミュニティ運営。

サスタビのメンバーに「サステナブルな旅、してる?」「サステナビリティって何だろう?」など、赤裸々に語っていただくメンバーインタビュー。今回は、サスタビを運営するピーストラベルプロジェクトの代表である、行方さんにお話を伺いました! 旅を通じて世界平和を実現するため、サスタビをスタート ―本日は、よ...
48年前に陸路で世界一周をして気が付いた。「旅は人を育て社会を創る」旅の効用

旅での経験は、その人の価値観の形成に大きく影響し、また、旅で得た見識は帰ってきた自分の暮らしや周りの社会にも知らず知らずの間に影響していく。
行方:
実は世界一周を始めた頃は、あまり旅の効用について意識したことはありませんでした。
当時は純粋な好奇心から「世界の人々はどんなことを考えて、どんな暮らしをしているのか」実際に現地に行って自分の目で見てみたかった。ただそれだけでした。
そして地球を一周して、世界の現状を実感してみたかった。
旅の効用を得るために旅に出ようだとかは気が付いてもいなかったし考えていない状態でした。
旅の最初の頃は、全てが物珍しく、日本と食べ物や文化がこんな風に違うんだ!住環境や衣服などととにかく日本との違いを一生懸命探していた覚えがあります。
SNSやネットが登場する以前のことなので、本や学校で見た写真などの事前知識でそれらを次々目にして、目に映る物すべてが新鮮に見えました。
はっきりした目的地を決めず現地に行って自由に街を巡っていると、地元の人々に声をかけてもらったり、病気になったときには助けて頂いたり、時には自宅に招いてご飯をご馳走してもらったりと多くの出会いを経験していく中で「住んでいる場所や文化が違っても、人間の本質は同じなのではないか」と徐々に感じてきたものでした。
違いを探すことと同時に、「人間の共通項って何だろう?」と問いながら旅することの大切さも知りました。
旅を始めてから、自分(日本)と他者の違いを探す旅から、現地の暮らしを知れば知るほど、そこで暮らす人々の思いや社会の仕組みに関心をもって旅するようになっていきました。
人は結ばれ、家族をつくり、子どもを産み育て、次の世代へと社会を継承していきます。また、人は社会を創って、助け合いながら安全に暮らすため、その土地に合った仕組みやルールを作ります。家族に愛情をもって暮らし、騙さない、嘘をつかない、相手を尊重するなど、私の行ったところは共通しているように思いました。
そのような暗黙のルールがないと、非常にストレスのたまる住みにくい社会になってしまうのでしょう。
相手を尊重する姿勢や相手の立場で物事を考えるなど、広い世界の中においても基本的な部分や目指している方向性は共通しているのだと思います。
世界一周をする中で、いわゆる定番の世界遺産などの大観光地も数多く巡りましたが、悠久の歴史を感じる巨大な遺跡をたくさん見始めると、初期の感動から徐々にその凄さに感動しなくなっていきました。確かに歴史の古さ大きさは、凄い、ただもっと旅先の暮らしの様子を知ることの方が、ずっと面白いと思いました。
旅の効用を考えると、岡村さんの旅のスタイルのように自由に旅する方が旅の効用は得られるものかもしれない気がしています。
また、旅をしながら、意識してゆっくりと考える余白の時間を持つことが良い方法なのかなと思います。
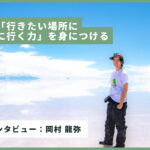
サスタビのメンバーに「サステナブルな旅、してる?」「サステナビリティって何だろう?」など、赤裸々に語っていただくメンバーインタビュー。今回は、「現代版なんでも屋」として旅をしながら働く岡村さんにお話を伺いました! 世界一周のきっかけは、「会社を辞めて暇だったから」 ―今日はよろしくお願いいたしま...
情報が飽和する時代に旅の効用を得るためには「不便益を楽しむ」

不便益とは
スマートフォンやインターネットから離れる、あえて手間のかかる手動の道具を使うなど、タイパやコスパとは逆の要素を取り入れることで得られる価値やメリットのこと
岡村:
とは言うものの、実際現代で余白の時間を作ることは難易度が高いですし、旅の効用に気が付く人はそうそう多くないようにも思います。
例えば行方さんが世界一周をされた当時はバスを何時間も待つみたいなことが当たり前だったところが、今は待ち時間自体も短くなっていますし待ち時間もスマホで本や漫画を読むなどいくらでもやることはあります。
おのずと考える時間が奪われてしまっている時代とも言えるのか、と寂しさを感じる部分もあったりしますね。
不便益を楽しむこと、ネット環境から離れ自分の考える時間を持つことはとても大事だと思います。ですが今はその不便益を楽しむことができない人が増えている感覚があります。
行方:
岡村さん、良い指摘ですね。一見遠回りに思えることでも、自分の頭で考えて行動したいろいろ苦労しても、途中のプロセスが後になって思い返してみると良い思い出となっていることは多いです。
岡村:
移動からホテルの予約、観光地巡りもほとんど人と話さずスマホ1台で完結させてしまう旅の仕方だと絶対に旅の効用は得られないと思います。実際に体験しないと行方さんが得た旅の効用は今の世代には伝えることが難しいなと。
ですがスマホなしで旅をすることを押し付けることも現実的ではないので、例えば3日間はスマホを手放してみよう、であったり我慢がない範囲でエンタメ要素を含む形で実践してみることが今の時代にも旅の効用を得るためにおすすめしたいです。
行方:
旅の本質的な部分ですね。自分で旅をしながら現地の情報に触れたうえで自分と対話して考えるような時間を持ってないと、一方的な情報だけがインプットされても、ほとんど後で記憶が残ってないみたいなことがあります。
旅のテクニックとしては、意識してスマホを少し使わない、考える時間を持ち思いついたことを書き留めておくことなどを意識することが重要なのではないでしょうか。
岡村:
全て不便な時代のやり方やアナログに戻ることを推奨しているのではなく、翻訳ツールなど、より意思疎通がスムーズになる、コミュニケーションの壁を取っ払う便利なものは積極的に取り入れるべきだと考えています。
自由な個人旅行の形がちょうどよいのかもしれません。その上で僕や行方さんのバックパッカー経験で得た旅の効用を抽出して人に伝えていくのであれば実際体験してもらわないとどうしても言葉だけでは足りない部分が出てきます。

「便利になるのはいいことだ」と私たちは思い込んでいます。しかし最も便利な選択肢が、「楽しむ」とか「満足する」といった観点では、1番良い選択肢になるとは限りません。不便から得られる利益、「不便益」なるものが存在するのです。旅を例に、不便のなかにある楽しさをお伝えします。 デジタル化する旅 ...
旅のリスク回避やスマホ活用について

行方:
バックパッカーのような自由な個人旅行だと、パッケージツアーと異なり、リスクはつきものです。切っては切り離せない問題だからこそリスク回避の知識も同時に伝えていくべきではないでしょうか。
岡村:
そうですね。「トラブルを事前に防ぐ方法」と「トラブルが起こった時に対処する方法」の二つも旅の効用に含まれると思います。
具体的には、前者はバスに乗り遅れないように早めに行動しようみたいなこと。後者は予定していたバスに乗り遅れてしまい、さらに手元のスマホで検索しても情報が上手く見つからない場合、周りの人に話しかけてみるとか次の日まで待つスケジュールに変更するなど臨機応変に対応することが挙げられますね。
行方:
自分から声をかけ地元の人と交流を楽しみながら旅を進めていくことも大切です。一方、旅行者に声をかけて何か買わせよう、だましてやろうといった人には注意してください。
宮野:
行方さんがもしも今の若者として世界一周をされるとしたら、旅の効用を得るためのスマホとの距離感についてどのように考えていますか?
行方:
様々な予約に使用するなど、効率よく旅するための道具としては有効活用すべきだと思います。
宮野:
旅慣れていない人はスマホをどう活用したら良いでしょうか?
行方:
特に初心者向けのおすすめの方法は、必要に応じてスマホを使いつつ、地元のガイドを活用しながら現地の情報を入手し、旅を楽しんでみてはいかがでしょうか。経験を積み2度目は自分で旅をしてみることもおすすめです。
宮野:
ガイドを使う!意外な回答ですね。なぜでしょうか。
行方:
先ほど話題に上がったリスク回避につながるからです。初めて海外旅行に行く人は事故などのリスクを心配されると思いますが、現地でガイドをお願いして初めの1、2日同行してもらい、その土地の人の暮らしや、街での移動方法、地元で人気な美味しい飲食店など教えてもらえばその後の一人旅にもつながるでしょう。
サスタビの今後の展望
行方:
そもそもサスタビはスタディツアーを集めたサイトを作り、それを社会に広めていこうとしていました。しかしちょうどコロナ渦と重なってしまいツアー自体もなくなりましたし、旅自体に行けない、旅先からも旅人は歓迎されないご時世となってしまいました。
これは「旅って社会的に意味のないものだったのか?」とすごく考えさせられる出来事でした。オーバーツーリズムなど、旅のネガティブな側面がクローズアップされることとなりました。旅自体が問題なのではなく、旅先にプラスとなるような旅の仕方もあるのではないかと考え、サステナブルな旅の仕方を探究することでその可能性を模索し始めました。
実際3年の月日が経ってみて、コロナもなくなり観光地も旅人を歓迎する状態になりました。オーバーツーリズムもメディアでもどんどん取り上げられるようになり、社会の中でも旅人の弊害っていうのも、一般の方たちにも広まりましたし、自分たちが発信している「より地域にプラスとなる旅をしよう」といった考え方も徐々に定着してきている手ごたえは感じています。
一方では環境とか社会とか、旅先に対して配慮していくSDGs的なことも叫ばれてきています。ただこれは旅に限った特別なことではなく、ごみをポイ捨てしてはいけないなどあくまで日常生活の延長線上ですし、大分意識も上がってきているのかなと思います。旅をすることで社会にプラスをもたらせることはあるのだろうか。今一度立ち止まって考える時期だと思います。
旅の効用は、旅を通じて人を育て、社会を作ること。とにかく皆さんには積極的に旅に出て欲しいと思います。
ただ、旅の仕方は多少不便でも苦労して体験して、地元の人の生活や考え方を深く知る旅をしてもらうことをサスタビとしては目指していくところですね。旅慣れている私でも、特に英語が通じない国に行くときは地元の人々の暮らしぶりなどを知りたくてガイドさんを使うことはありますよ。
また、「サステナブル」という言葉にもこだわりすぎず、今後活動していけたらと思います。「サステナブルな旅」のニーズはあるかと思うのですが、具体的な「サステナブルな旅」の方法が良いかわからないと感じている人に対して、具体的な旅の提案ができれば良いなと考えています。
岡村:
もしかすると国内旅行より、海外旅行に可能性があるかもしれませんね。これは極端な意見かもしれませんが、いくら国内を旅しようが、やっぱり一度海外に行った経験には勝てないじゃないかと思います。個人的にも皆さんに一度は海外に出て欲しいなと思いますし。一人だったら行けない場所、一人だったらガイドが高くて手配できないからこそみんなで行くみたいなツアーのようなことはサスタビでプロデュースできるならぜひやりたいです。
行方:
そういうツアーの中で2日間か3日間、自由時間を設けるなんて方法もありますしね。
岡村:
その先に見えるものが、「ピーストラベルプロジェクト」につながっていくのではないかと。最後は世界平和に相互理解と世界平和っていうのにつながっていくっていうのは、この事業の一番の目的であり僕たちがやる意味があるのではないかとすごく思います。

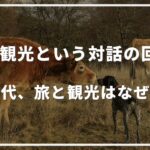

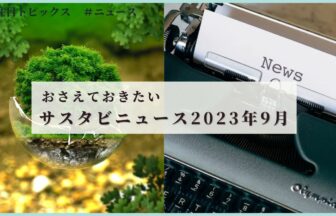

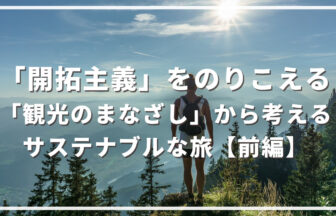
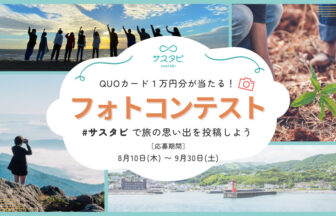


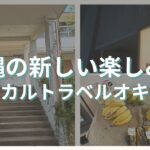


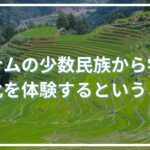



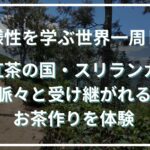





この記事へのコメントはありません。