「人新世」
20世紀以降、人間の活動は地球のシステムに深刻な影響を与えつづけ、それはもはや地層すら変化させているのではないか。「人新世」という言葉は、そのような現代の地球の現状が、地質年代(地質時代)にまで爪痕を残している可能性を表現するために提案された言葉です。オゾン層破壊について研究をし、1995年にノーベル化学賞を受賞したパウル・クルッツェンとユージン・ストーマーの二人によって提唱されました。
現在の地球は、氷河期を経ておよそ1万7千年前に始まった「完新世」にあたります。人類の誕生はおよそ700万年前とされるので、中新世と鮮新世のあたりから人間の足跡が地球に残されてきたということでしょうか。
日本地質学会が、国際地質科学連合(IUGS)の国際層序委員会(ICS)に基づいて作成した地質年代表(ChronostratChart2023-09Japanese (stratigraphy.org))を挙げておきます。年代表を見れば、人間の歴史は地球全体のそれと比較にしてきわめて短いものであることがわかります。そして「人新世」という新しい地質年代(候補)の名は、とりわけ20世紀以降のきわめて身近な人類のおこないが、この地球の長い歴史に刻まれるほど大きな影響を地球全体に及ぼしているということを示すものなのです。そして人新世は、議論を経ておおよそ1950年以降からはじまったという理解がなされています。

土に還ることのないプラスチックやコンクリートなどの物質が大量生産・大量消費され、長い将来にわたって地面や海洋に蓄積し続けるであろうこと。プルトニウムなどの核物質が地球上に飛散するリスク。人間活動による空気中の二酸化炭素量の増加。そうした、20世紀後半以降の私たちの営為がもたらした地球環境の物質的変化と、地質にまで至るその痕跡は、もはや無視することのできないレベルに達しているとされます。
今回の記事ではこの「人新世」について、その言葉が私たちに伝えようとしているインパクトをしっかりと理解するために、まずは「人間と自然」をテーマとした回り道から説明をはじめたいと思います。
地球に対する想像力
地球というひとつの運命共同体を人間が真の意味で認識したきっかけは、いつでしょう。それはもしかすると、人類による宇宙探査、そして宇宙から撮影された青く輝く地球の写真であったかもしれません。宇宙から撮影された地球の写真は、通常では見ることのできない「地球の外部」からその全貌を見る視野を私たちにもたらしました。そのとき人類は、地球をはじめて客観視することができたと言ってもいいでしょう。何かを客観視する、すなわち自分自身という「主体」から切り離された「客体」として物事を捉えるためには、そのような「距離」が必要となります。

宇宙というと、生活からかけ離れた経験の舞台のように思われるかもしれません。ですがもう少し身近にも似たような経験のきっかけは存在します。たとえば飛行機に乗ると、少し前まで自分が立っていた場所や暮らしていた地域が離陸後に瞬く間に遠く、小さくなってゆき、それと同時に広大な陸や海が視界に広がっていきます。それでもなお捉えきれない地球の大きさや、自らの生活する地域がその広大な地平にまさしく組み込まれ、地続きに繋がっているという事実は、しばしば私たちを驚かせるでしょう。
自然とどう向き合う?客体?それとも?
こんにち、地球環境の問題やグローバルな社会的課題はますます深刻なものとなっています。そしてこの現状を引き起こしてきたのは、これまでの私たちの生活や政治にほかなりません。
さて、冒頭で、「地球を客観視するきっかけ」のお話をしました。客体化すること、すなわち自らと引き離してその全体像や様相を視野に入れることで、対象を客観視するような視点のことです。そのような視点、そして「地球に対する想像力」は、地球規模で生じている問題を可視化させ、冒頭でも述べたように「地球というひとつの運命共同体(を何とかしなければならない)」という認識をもたらす可能性を持っています。
余談ですが、ちなみに「客体化」の例で、私たちに最も身近な実践例はおそらく「自己紹介」です。自己紹介をするとき、私たちは自分自身という存在を他者に理解してもらうために、自分のことを客観的に捉え直しています。そのとき、鏡に映った自分自身を見るように、私たちは自分のことをある意味で「外部」から捉えています。ちなみに社会学では、このように自分自身で自己のことを考えたり、反省したり、作りかえたりする営みのことを「自己再帰性」と呼ぶことがあります。再帰性とは、自分から出た「やじるし」が螺旋を描いて自分自身に戻ってくるような動きのことですね。自分の言動や行動に問題が無かったか自ら検証し、次の行動に活かしていくような「自己再帰性」は、ある意味でサステナブルな旅にも求められているのかもしれません。
しかしながら、そのように地球や自然のことを「自らと切り離して考える」という客体化の視点こそが、今日の地球環境を導いてきてしまったという側面も存在します。どういうことでしょうか。
人間から切り離される「自然」
「近代」という言葉で、みなさんはどのようなことをイメージするでしょうか。近代的なもの、先進的な技術、発展、幸福……この言葉は、何か私たちを「前進」させてくれるような響きを持っているかもしれません。教科書的な説明では、時代区分としての近代は産業革命に端を発するとされることが多いですね。
「近代」について、強引に、そしてきわめて単純化して一つの説明を加えるとすれば、それは「文化と自然(あるいは社会と自然)に線引きをする認識枠組み」ということができます。自然と文化、自然と社会はそれぞれ別物であって、異なる領域に属すると捉える考え方のことです。この視点は、次のような考え方へとさらに展開していきます。すなわち人間は文化的に生きる存在であり、社会を構成し、科学技術や知恵を用いる。そして、自然とはそうした人間の文化や社会の外部にあるものであり、かつ、人間が科学技術を用いてコントロールすることができる存在である、と。
科学や技術が自然に対して行ってきたこと。それは、自然を観察し、分類・命名し、分析しコントロールするという一連の営みです。それは人間が自らを自然と切り離し、自然を「人間によって観察され、コントロールされる客体」と位置づけて初めて可能になるものです。冒頭で述べた宇宙開発と地球の客観視も、言うまでもなく人類の近代における科学技術的発展の産物ですね。そして人類の宇宙への旅は、地球という自然を人間がその外部に脱出することを通じて自らと切り離す、まさしく線引きの思考の極致ともいえる実験でもあったのです。

「自然」はコントロールできる?
しかしながら、人類がすぐに気づき始めたのは、自然を人間の一存によって完全にコントロールすることなどできないという事実でした。地震や火山活動、気候変動、海洋環境の変化、生態系の変化……それらは今日、私たちの生活に深刻な影響をもたらしています。地震を発生しなくさせたり、気候変動を即座に止めたりするようなことはできません。自然は人間の外部にあり、ゆえに操作したりコントロールしたりすることができるという近代的な思考は、限界を突きつけられています。
また、近代によって引き起こされてきた問題を「近代化のさらなる発展」によって乗り越えようとする視点にも更なる問題が存在する可能性があります。ウルリヒ・ベック、アンソニー・ギデンズ、スコット・ラッシュは、近代的な思考や開発がもたらしてきた問題を、その原因をつくった近代的な思考によって解決しようとすることを「再帰的近代化」と表現し、それは近代を乗り越えるものではなく「近代をさらに徹底」しているだけであると指摘しました(1)。たとえば原子力発電のリスクを、さらに安全で機能的な原子力発電技術や施設開発によって減じようとするような考え方であり、またそのような考え方を最優先するような思考が一例でしょう。ただし、もちろん近代的・技術的に課題を乗り越えることがすべて問題であるわけではありません(それ以外の考え方を無視したり、「近代的思考より劣ったもの」と位置づけたりすることには一層の注意が必要ですが)。
重要なことは、気候変動をはじめとする地球環境の問題は、「自然をコントロール」しようとしてきた近代的な思考を原因としているという点です。自然を人類から切り離された、操作可能な対象と位置づけることで、人類にとって自然は開発や支配の対象となりました。自然を支配し、自然の問題を克服するために科学技術が投じられ、その結果として、自然は「資源」へと位置づけられてきたといえます。すなわち森林は木材として、海洋は水産資源として、土地は不動産資本の源泉や、あるいは油田の可能性などとして。そのようにして自然を「資源」すなわち人類の生活の材料や道具として位置づけてきたからこそ、私たちの現在の便利な生活があるとともに、気候変動や海洋環境の変化といった深刻な問題も現れてきたのです。
自然と結びつく思考へ
自然を支配やコントロールの可能な「客体」として捉えること、そしてそれが可能な「主体」として人間を位置づけること。現在生じている環境問題を解決していくうえで、そのような認識の枠組みは再考されるべきものです。
先ほど「余談」として、自己再帰性や自己客体化のお話をしました。今必要な視点は、そこで述べたお話の延長にあるかもしれません。すなわち「人類と自然は(あるいは文化や社会と自然は)つねに再帰的に結びついているものである」という視点です。自然をコントロールできるという「驕り」ではなく、ともに影響関係にある共生のパートナーとして、自然と向き合っていく必要があるということですね。自然も社会も文化も深く結びついているのであり、切り分けることはできません。

「自然と向き合う術」としての旅を想像しよう
そのような視点の獲得のために、旅や観光が有用である可能性も存在します。
むろん、観光は「近代」にはじめて成立した産業であり、マスツーリズムや大規模観光開発、そして今日のオーバーツーリズムをはじめとする様々な深刻な問題を自然や社会にもたらしてきました。それゆえに、観光をつうじて観光の問題を乗り越えようとすることは先述した「再帰的近代化」の線上にあるものです。ただし、だからといって観光を完全に手放す必要はないかと思われます。近代がもたらした問題を乗り越えようとするために、「近代以外のもの」すなわち「前近代的なもの」に理想を求めることはユートピア思想や懐古主義にほかならず、それもまた一定の問題を抱えていますし、現状の問題含みな観光を「臭い物に蓋をする」かのごとく放置することも問題でしょう。考えるべきは、観光の抱えてきた問題をいかに改善しながら、新しい観光のあり方を構想していくかという点にあるのであり、いうなれば「再帰的近代化」を脱出することではなく、「いかに再帰的近代化を果たしていくのか」ということにあるのかもしれません(または、今回の記事では触れませんが、「脱成長」をキーワードとする考え方にも別の道があるのかもしれません)。
観光や旅を、「これまでとは異なる新しいかたちで自然と向き合うきっかけ」のひとつに位置づけることはどうでしょうか。
たとえばエコツーリズムやグリーンツーリズムは、自然について理解を深めたり学んだりすることをつうじて、自然を「開発対象」や「資源」として捉える視点から、人間と不可分に結びついた存在として捉える視点へと移行するきっかけになるものといえるでしょう(もちろん、自然を「観光資源化」しているという点で、すべてを手放しに評価できるわけではないと思います)。日常生活では得られなかった自然との向き合い方を学ぶ方法、術(すべ)としての旅や観光。そのように捉えるとき、旅先で自然体験プログラムに参加することや、その地域の人々の自然との向き合い方を学ぶことにさらなる可能性がみえてくるでしょう。
「サスタビ20ヶ条08 自然体験型プログラムに参加してみよう」https://sustabi.com/blog/4575/
「人新世」と称されるまでになった人間活動と自然への影響を無視することはできません。そして今日、SDG’sや持続可能性をキーワードに、企業活動や私たちの日常生活では自然やエネルギーとの向き合い方についての再考が進んでいます。旅や観光においても、その流れを意識していく必要があるでしょう。私たちが自然と結びついていることを学ぶ術、自然と向き合う方法を体得する術としての観光や旅の可能性について、ぜひ一緒に考えてみませんか。
参考文献
W. ベック、A. ギデンズ、S. ラッシュ(1997)『再帰的近代化――近現代における政治・伝統・美的原理』松尾精文、小幡正敏、叶堂隆三訳、而立書房。
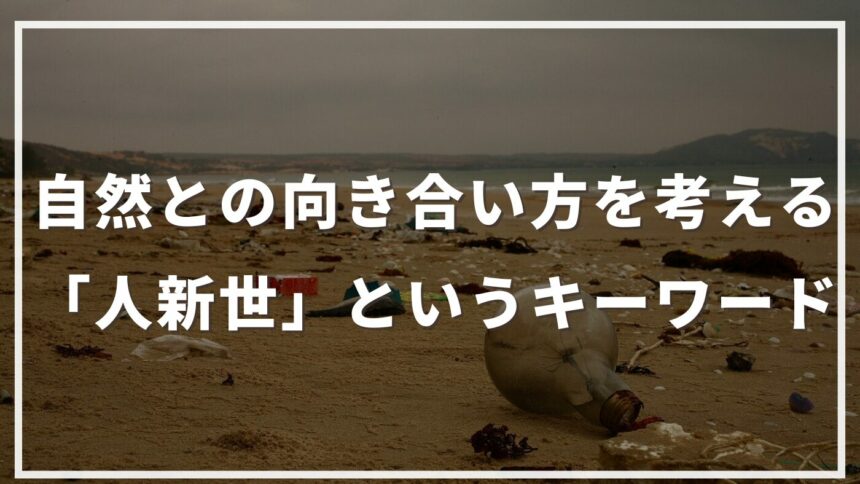




















この記事へのコメントはありません。