 こんにちは、サスタビ運営の岡村です。今回は代表の行方とともに、約1週間ラオスを旅してきました。
こんにちは、サスタビ運営の岡村です。今回は代表の行方とともに、約1週間ラオスを旅してきました。
この旅の目的は、行方が長年支援してきたラオスの学生たちの今を見に行くこと。とはいえ、訪問はそれだけにとどまらず、学校や支援施設の見学、現地の起業家との交流、大自然の中での体験、そしてラオスならではの食文化まで──。密度の濃い7日間となりました。
本記事では、その中でも特に印象に残った出来事をダイジェストでお届けします。
そもそもラオスとはどんな国か

ラオスは、東南アジア唯一の内陸に位置しており、自然豊かで、山や川に囲まれた、のんびりとした空気が流れる国です。
初めて訪れたとき、時間がゆっくり進んでいるような感覚になったのを今でも覚えています。人々はとても穏やかで親切。言葉が通じなくても、笑顔やしぐさで心が通じ合う瞬間が何度もありました。
華やかな観光地は少ないけれど、そのぶん日常の暮らしや文化にふれる旅ができるのがラオスの魅力。せかせかした日常を忘れて、ふと立ち止まるような旅がしたい人にぴったりの場所です。
ラオスの教育現場を訪問

今回の旅では、小学校、高校、大学の3つの教育機関を訪問しました。あいにく夏休み期間だったため生徒の姿はほとんど見られませんでしたが、先生方とじっくり話す機会があり、ラオスの教育が抱える課題について学ぶことができました。
とくに印象的だったのは、ラオスの起業家や教育関係者に「ラオスが今、一番困っていることは何か」と尋ねると、全員が揃って「教育」と即答したことです。

たとえば小学校では教科書が翻訳されているものの、実際の授業時間と内容が一致しておらず、実用性に課題があるとのこと。また、地域によっては壁のない校舎もあり、雨が降ると授業そのものが中止になってしまうケースもあるそうです。単に教材を提供するだけでは解決できない、構造的な問題が浮き彫りになっていました。
またトイレの数が足りておらず、すでにあるトイレも衛生的に問題があるため、生徒がトイレを使いたがらない、もしくは病気のリスクがある状態も報告されていました。
こうした環境下では、義務教育を終えてもかけ算ができないまま高校を卒業する生徒もいるという話も耳にするなど、私にとって非常に衝撃的でした。

さらにラオスの名門とされるラオス国立大学も、現在は定員割れが起きているそうです。その背景には、大学を卒業しても一部の専門職を除いて高卒とほとんど変わらない賃金水準であることや、タイの大学に進学し、そのまま就職する学生が増えているといった現状があります。
これらはあくまで現地で聞いた話を私なりにまとめたもので、正式な統計データに基づくものではありませんが、関わった多くの方々が同様の見解を口にしていたことが印象的でした。

ヴィエンチャン高校では、長年サスタビ代表の行方が支援してきた高校生やその卒業生たちと初めて対面で交流。普段の授業の様子を見せてもらい、その後は一緒に食事をしながら、生徒たちによる歓迎セレモニーまで開催していただきました。

このセレモニーでは、先生も事前に知らされていなかったというほど手の込んだセレモニーが用意されており、各生徒が自分の民族に伝わる伝統的な踊りを披露したり、ギターの弾き語りやカラオケ、サプライズのプレゼントまであり、心から温かさを感じました。

最後には、生徒たちが生活している高校の寮も見学させていただきました。行方が支援しているのはラオスの地方出身の子どもたちが中心で、みな親元を離れてこの寮で暮らしながら学んでいるとのこと。ラオスに来て、高校の寮を訪れる機会があるとは思ってもいなかったので、非常に興味深い体験となりました。
社会課題と向き合う現場へ

現地では、「カフェパ」というカフェを経営するNuiさんのお店を訪問しました。彼女が扱うお皿やパッケージ用品は、障がい者の方々が働く支援施設で製造されており、実際にその施設にも案内していただきました。

印象的だったのは、Nuiさんが「支援ではなくビジネスとして」仕事を発注しているという点。クオリティに妥協せず、あくまでも“プロの仕事”として接している姿勢に感銘を受けました。
販売されている製品もクオリティが高く、自分も普段使い用にポーチを購入しました。普段はあまりお土産を買わないのですが、思わず手に取ってしまったほどです。

またNuiさんのお店ではラオス産のコーヒー豆も扱っており、その豆の選別を足の不自由な方が担っているとのことで、作業をしているご家庭にも訪問させていただきました。どれが良い豆かを選り分ける手作業は非常に繊細で、自分には見分けがつかず、想像以上に根気のいる作業だと感じました。

続いて訪れたのは、サスタビ代表・行方が評議員を務める「民際センター」のラオス拠点。ここでは日本からの個人支援による「ダルニー奨学金」などが運営されており、現地スタッフの方々と現在の運営課題などについて意見交換を行いました。
ちなみに、この奨学金は1人の子供に対して年間14400円/年間から始められるそうで、私自身この訪問で初めてその存在を知りました。これだけラオスの方々にお世話になった今、これは何かの縁だと感じ、支援を始めてみようと思っています(※申込みは時期があるそうなので要確認です)。<<ダルニー奨学金について >>
現地ビジネスと起業家のリアル

今回の旅では、AMZグループ代表のシータラさんにも大変お世話になりました。彼が関わる複数の企業や施設を見学させていただき、現地のリアルなビジネスの現場に触れることができました。
訪問先には、ラオス現地法人として初めて、ラオス国内向けインターネットインフラ事業を展開するGMO-Z.com LaoやICTでラオスの国を豊かに」というスローガンのリョービラオといった日系企業のラオス拠点や、養豚場、人材育成施設などがあり、それぞれの現場でどのような人が働き、どんな業務が行われているのかを実際に見ることができました。

とくに印象的だったのが、「NMS Lao」という施設。ここはラオス政府公認の技能実習生送り出し機関で、日本で働くことを目指すラオス人たちが共同生活を送りながら、日本語やマナーを学んでいます。
ラオスの方々は、性格的に控えめで穏やかな人が多く、日本人と似た気質があるといわれています。そのため、実際に日本に渡ったラオス人技能実習生は、日本社会にも比較的スムーズに適応しているとのこと。

施設では、現地の若者たちが日本語で自己紹介をしてくれたり、寮の様子を案内してくれたりと、非常に温かく迎えてくれました。ここで出会った彼らと、いつか日本で再会できる日が来ることを楽しみにしています。
また、AMZグループ以外の現地起業家の方々とも経営に関する意見交換をさせていただき、行方の活動の一端に触れる貴重な機会となりました。
ラオスの自然・文化・アートを味わう

今回の滞在では、観光もバッチリ楽しみました。
サスタビが掲げる「旅の20か条」の中にある「自然体験型プログラムに参加しよう」の実践として、ヴィエンチャン中心部から車で約1時間の場所にある「La Forêt(ラフォーレ)」というエコアクティビティ施設を訪れました。
この施設では、船で対岸へ渡って入場するところから始まり、すでに日常とは切り離された“非日常”の空気を味わえます。敷地内では、スカイウォークやサイクリングなどが体験でき、移動には電動カートも使えます。

スカイウォークは、高い木の上に吊り橋が架けられたスリリングなコースで、高所恐怖症の方には少しハードかもしれませんが、安全性は確保されており、景色は圧巻です。
また、木々の上に設けられた展望ウッドデッキにはカフェが併設されており、自然に囲まれながらゆったりとした時間を過ごすことができます。さらに、ジップラインなどのアクティビティも用意されていて、子どもから大人まで楽しめる空間でした。

他には「Lao Art Museum(ラオアートミュージアム)」にも立ち寄りました。廃材を活用した巨大アートが多数展示されており、その規模と密度に圧倒されました。特に仏教文化をテーマにした木彫作品が印象的で、展示されている空間自体も非常に美しく、建築物としても一見の価値があります。

また、今回は「公共交通機関を使おう」というサスタビの考え方に沿って、2021年に開通した中国・ラオス高速鉄道(通称:ラオスの新幹線)を利用し、ヴィエンチャンからバンビエンまで移動。
鉄道ではありますが、飛行機のように乗車20分前には駅に到着してパスポート提示や荷物のセキュリティチェックが必要となるのが驚きでした。
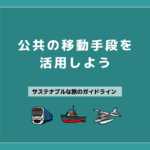
自家用車やタクシーで移動するのではなく、公共の移動手段を活用しましょう。旅先で車を使わないだけでもサステナブルな旅に大きく近づきます。また、徒歩や自転車で移動すれば、地球に負担をかけずに町の雰囲気も味わえるというメリットも。...

バンビエンでは、洞窟探検や滝周辺のトレッキングを通してラオスの自然を満喫。現地の方に案内していただいたことで、個人旅行では得られないディープな体験ができました。
特にラオアートミュージアムは、2025年開館のまだ新しいスポットということもあり、近年訪れた国々の中でもトップレベルで面白く、今後注目されること間違いなしです。ぜひ訪れてみてください!
ラオスの“食”から社会を知る

最後に紹介するのは、ラオスの「食文化」についてです。
ラオス料理は、タイやベトナム、中国の影響を受けながらも独自性が強く、主食は「カオニャオ(もち米)」。竹のかごに入れて蒸したものを手でちぎり、料理と一緒に食べるのが一般的です。
香草をふんだんに使うのも特徴で、パクチーやミントなどが多用されています。タイ料理ほど辛くないものが多い印象ですが、卓上の調味料を加えると一気に激辛になるので注意が必要です。
印象に残った料理を3つ紹介します。
ラープ:

ひき肉とハーブを和えたラオスを代表する料理。使う肉によって名前が変わり、鶏肉なら「ラープ・ガイ」、牛肉なら「ラープ・ヌア」と呼ばれます。今回は珍しい「七面鳥のラープ」も体験しました。一般的ではないそうですが、とても美味しかったです。
カオピアック:

ラオス風うどん。米粉とタピオカ粉を使ったモチモチ食感の麺で、滞在中何度も食べました。辛い調味料は少量でも強烈なので、入れすぎ注意です。
シン・ダート:

ラオス風の焼肉鍋。中央がドーム状の鉄板で肉を焼き、周囲にスープを張って野菜や春雨を煮るというスタイル。タイのムーカタと似ていますが、ラオスでは特に家族や仲間で囲んで食べる文化が根づいており、タレもニンニクやチリを使った特製のものが主流です。
料理の美味しさもさることながら、「誰と食べるか」「どんな空間で食べるか」がラオスでは特に大切にされていると感じました。
ラオス滞在まとめ

今回で3回目となるラオス訪問でしたが、これまで以上に現地の人々と交流し、文化や人柄に深く触れることができ、ラオスへの愛着が一層深まりました。
特にこれまで短期滞在が多かった首都ヴィエンチャンですが、今回はじっくり滞在したことで、その奥深さや魅力を改めて実感。カフェも多く、作業や滞在にも向いていると感じました。
また、2025年6月1日から日本人のラオス滞在可能期間が15日から30日に延長されたことも大きな変化です。物価も安く、ネット環境やカフェも充実しているため、デジタルノマドや長期滞在者にとっても今後ますます注目される場所になると感じました。
みなさんも、ぜひこのラオスという国を、学びと出会いのある旅先として訪れてみてください。
立命館大学大学院修士課程修了。専門は情報理工。NTTデータ入社後、大規模システム開発の維持管理やビッグデータを用いた観光分析を担当。世界一周後、場所にしばられずに働くを追求してITに特化した現代版なんでも屋を起業。チェコ親善アンバサダー、銀河高原ビールアンバサダー。通称、シャンディ。

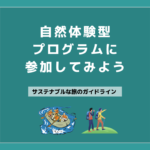
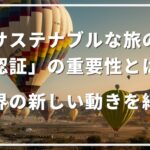


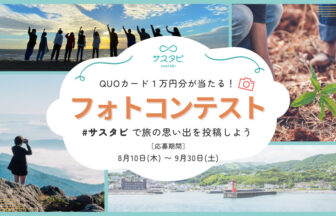
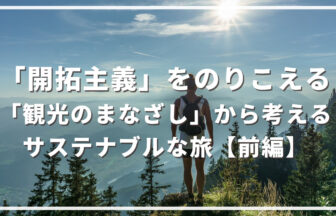

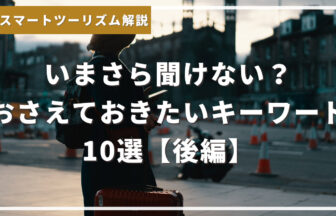

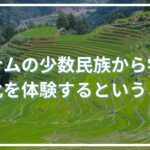


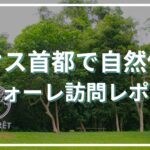









この記事へのコメントはありません。