生活や環境を支えている仕組みを学ぶ、インフラツーリズム
前編では、私たちの行動や移動を可能にしてくれている「インフラストラクチャー」の特徴について整理をしました。インフラは私たちにとってあまりにありふれている存在であるがゆえに、たとえば「この水はどこから来ているのだろう」「この電気はどうやって作られて私の家に運ばれているのだろう」などと疑問に思うことは、なかなかありません。

私たちの生活をよりサステナブルにしていくためには、「そこにあることが当たり前」になっているインフラに敢えて視点を傾けることが重要ですね。そうすることによってはじめて、日々使用しているエネルギーや資源、設備のサステナブルな用法を考えることができるようになります。
後編でお話する「インフラツーリズム」はまさに、観光を通じてインフラストラクチャーに意識的になり、そこから学びや気づき、楽しみを獲得する実践だといえます。
北海道で広がるインフラツーリズム
北海道はインフラツーリズムの先行的な例を実践している地域です。広大な土地を有し、そこにさまざまなインフラ施設を抱えている北海道では、普段は一般人が入ることのできない公共施設や工場を観光客向けに開放することで、観光客を誘致しています。技術者の高齢化や人手不足が課題となっているインフラ産業の担い手を呼びかけることもねらいのひとつとなっているようです(※1)。

国交省・北海道開発局の公式ホームページには「インフラツーリズム」のページも(リンクはこちら)。そこでは、見学可能なダムや発電所などのインフラ施設について、それぞれ概要やアクセスなどの情報をみることができます。
2022年度には北海道古平町にある「古平漁港」を中心に組織したインフラツアーが実施され、そこでは漁港というインフラの見学に加えて、「サケ」を捌く体験やイクラの醬油漬け作りの体験もツアーの醍醐味でした。インフラとしての漁港を単体として見学するのではなく、インフラをその地域の食や文化、自然環境と一緒に学ぶことに重きを置いているツアーである点が興味深いと思います。

漁港のほかにも、北海道のダムや公共土木施設について理解を深めるインフラツアー(北海道庁ホームページ参照)などさまざまなツアーが北海道では組織されつつあります。現地の旅行会社との連携も進んでいます。
インフラツーリズムが可視化する「当たり前」
インフラツーリズムには、「不可視なものの可視化の契機」という可能性があると思われます。
先述したように、サステナブルなエネルギー利用や消費を考える場合、資源やエネルギーに意識的になることは必要不可欠な最初の一歩です。蛇口をひねれば水が出る、スイッチを押せば電気がつく、スーパーにいけば肉や野菜が売られている……そのような「当たり前」がどのような仕組みで成り立っているのか、電気や水や食べ物はどう作られてどこからどうやって運ばれているのか。そうした「これまで当たり前であったこと」「これまで特に意識せずにいたこと」「見てみぬふり(不可視化)をしてきたこと」に疑問を抱き、意識することが、サステナブルな取り組みのためにはきっと必要ですね。
インフラツーリズムはまさにそのプロセスを学ぶことができる旅だといえるでしょう。「当たり前を当たり前ではなくする観光」「不可視なものを可視化させる観光」がインフラツーリズム(の可能性)なのであり、それによって得られる気づきはサステナブルな実践にまるごと活かすことができるのです。
旅人の武器、馴質異化の視点
当たり前からの脱却。それはサステナブルな実践に必要な姿勢であると同時に、旅をより豊かにしてくれる姿勢でもあります。
ここで、それにピッタリな言葉「馴質異化」について紹介したいと思います。馴質異化(making the familiar strange)とは、当たり前だと思っていたものを「異化」すること。ありふれた景色を別の角度から新鮮に捉えなおし、新しい発見を得ようとすることをいいます。見慣れたものを見慣れてないものに変化させることであり、そのような意識のあり方=姿勢のことです。
旅人のみなさんは、この馴質異化の視点を気づかぬ間に鍛錬しているのかもしれません。
ちなみに馴質異化と対になる「異質馴化(making the strange familiar)」という言葉もあります。これは「一見すると奇妙で、とても理解できなさそうなものを自分から切り離すのではなく、自分にとって理解可能なものにしようとすること」だといえます。見慣れてないものを見慣れたものにしようとする意識です。
馴質異化と異質馴化は、どちらも「他者理解と自己変容」に大きく役立つ姿勢です。どちらも「相手を新しいかたちで理解しようとする実践」であり、異郷の地を訪れる旅人には必要不可欠なものだといえるでしょう。
インフラツーリズムはまさに、インフラというありふれたもの(当たり前すぎて透明になっているもの)を再発見し、そこから学びを得ようとする馴質異化的な旅のあり方ですね。
「当たり前」を「驚きや発見」へと変化させていく馴質異化の視点は、通常の旅や観光においては地域の魅力発見に役立ちます。そして、ことサステナブルな旅においては、私たちの生活や旅を普段から成り立たせてくれている仕組みに意識的になり、サステナブルな方向にむけて行動変容していくための第一歩になるものだといえるでしょう。それは、ひいては旅をつうじたサステナブルな社会の実現に結びつくと思います。

よく旅し、よく学び、よくサステナブルに
馴質異化は、普段の生活でも実践することができます。普段の何気ない散歩道でどんな新しい発見ができるか考えることは、馴質異化のトレーニングになると思います。ちなみにこれは個人的な意見ですが、馴質異化(そして異質馴化)を鍛えるもっともよい方法は、きっと「旅をすること」と「学ぶこと」だと思います。旅と学びはそのどちらも、新しい視点を獲得し、当たり前を異化しようとする営みにほかならないからです。
旅も、学びも、そしてサステナブルな社会の実現も、すべて「当たり前を問い直す」ことからスタートするのかもしれませんね。
※1.日本経済新聞(2023年3月25日)「インフラ観光、北海道が先行 学生ガイド/暮らし体験 ダム湖の氷で回転遊び」p.37。
サスタビ外部アドバイザー担当。北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院 専任講師。立教大学大学院観光学研究科 博士課程後期課程修了。博士(観光学)。専門は文化人類学、観光研究、モビリティ研究。北海道札幌市出身。


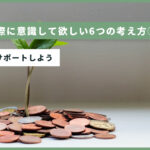

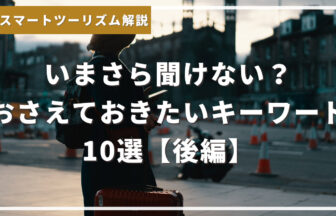


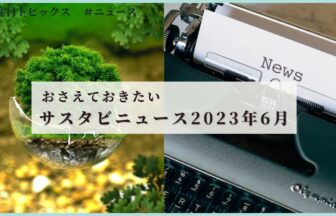

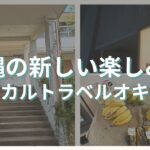


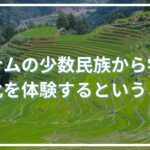



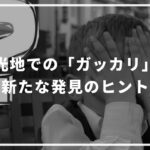




この記事へのコメントはありません。