観光地での「ガッカリ」
観光や旅に「ガッカリ」はつきものです。
混んでいた。閉店していた。店員さんの態度が悪かった。天気が悪かった。景色が良く見えなかった。疲れた。値段が高かった。写真では映えていたのに「リアル」で目にすると大したことなかった。味は微妙だった。部屋の壁が薄かった。温泉がぬるかった。着替えを忘れた。飛行機が揺れた。あまり相性が合わない人と同室になった。などなど。
観光や旅は楽しさや興奮、満足感にあふれているように見えて、じつは落胆や「期待外れ」も少なくありません。みなさんはどのような「ガッカリ」を経験したことがあるでしょうか?今回の記事では、この「旅先でのガッカリ」について別の角度から捉えてみたいと思います。

旅や観光は「期待」がなければ始まらない
まず確認しておくべきは、観光や旅において「ガッカリ」や「期待外れ」は「必ず」生じるものであるということです。それは、旅や観光が「事前に抱くイメージ」を必要不可欠とした営みであるからにほかなりません。
観光は、「その場所に行きたい」という欲求からはじまります。しかしその欲求そのものは、身体の内奥から自然に湧き出てくるものではありません。名前も知らず、景色をまったく見たことのない場所について、「観光に行きたい」と思うでしょうか? 観光に行きたいという欲求は、その場所についての先行イメージがなければ生まれてこないのです。
では、「場所はどこでもいいからとにかく観光に行きたい」という気持ちはどうでしょうか。実はそれもまた、どこか特定の特徴を持った風景のなかで特定の行為をしている自分自身を思い浮かべながらにして生まれるものであるはずです(旅館でのんびりしたい、贅沢な食事を食べたい、見たことのないものを見たい…そうした気持ちは、特定の映像イメージや「妄想」とともに抱かれているはずです)。

そうしたイメージを作り出しているもの。それが、「メディア」です。SNSやテレビ、ガイドブックや電車内の広告、小説に描かれる情景やアニメの舞台、友人からの伝聞情報など、さまざまなものがメディアに含まれます。そして、そうしたメディアに描かれたイメージを実際に見たい・追体験したいという気持ちが私たちを観光へと駆り立てているといえるでしょう。観光に関わるメディアは、そうした事前の「期待」や「予想」をつくりだし、商品化してきました。
観光や旅は「事前に抱く期待」と必ずセットなのです。特定の場所や目的地についての部分的な「先行イメージ=期待」のない旅や観光はおそらくありえません。○○を食べたい・したい・見たいといった気持ちや、「ここにいけばこういうことが楽しめるだろう」「あんなことやこんなことができるはず」「こういう自分になれるはず」といった期待感が必ずあるはずです。旅や観光は「期待」がなければ始まりません。
「期待外れ」もまた「期待」から生じる
期待があってはじめて成立するものが観光や旅であるならば、そこにはかならず「期待外れ」も生まれます。もともと抱いていた期待よりも良い体験ができた場合には「満足」として、そして反対にもともとの期待を下回る経験となった場合には「ガッカリ」として、私たちは経験することになります。事前の期待とまったく同じ体験をする「期待通り」の経験もあるでしょう。
観光や旅では、事前に想像もできなかったような新たな出会いや発見、経験もたくさん生じます。それらは「事前の期待」の外部にある経験のように見えます。しかしそれら「予想外」の現象もまた、「事前の予想」があってはじめて認識されるものだというべきでしょう。「期待外れ」は「期待」がなければ生まれず、「予想外」は「予想」があってはじめて成立するものにほかなりません。

「ガッカリ名所」
ここで余談ですが、「世界3大ガッカリ名所」や「日本3大ガッカリ名所」なるものも存在します。
世界では、シンガポールの「マーライオン」、ベルギーの「小便小僧」、コペンハーゲンの「人魚姫像」が、そして日本では札幌の「時計台」、高知の「はりまや橋」、そして長崎の「オランダ坂」が3大ガッカリ名所として知られています。
これら「ガッカリ名所」においては、「ガッカリすること」が期待されているという倒錯が生じています。ガッカリ名所でガッカリできなければガッカリしてしまうという面白い状況です。

ガッカリは「先入観」「ステレオタイプ」を自覚するきっかけに
「ガッカリ名所」はさておき、今回の記事で念頭においている「ガッカリ」は、冒頭に列挙したように観光地が混んでいたとか、店員さんの態度が悪かったとか、地域や施設が思っていたより汚かったなどといった(ある意味で)観光にありふれた「期待外れ」や「落胆」のことを指しています。そして当然、観光においてガッカリはしたくないものですよね。嬉しい意味、期待以上という意味での予想外は大歓迎でしょうが、満足度に欠けてしまうという意味での期待外れはできれば避けたいと思うのが当然です。
他方で、今回の記事で注目してみたいのは、「観光地でガッカリすること」が再帰的な自己発見につながる可能性についてでです。
観光地を訪れてガッカリすることは、見方を変えれば「自らが事前に一定の先行的なイメージを抱き、それを観光地に投影していた」という事実に気づく瞬間でもあるといえます。
「自分のことを笑顔で暖かく迎えてくれるはず」「ホスピタリティを存分に発揮してくれるはず」「道もきれいに整備されているはず」「お店が今日も開いているはず」……等々。こうした事前の期待やイメージは、じつは観光地側の人びとに対する一方的なイメージの投影(押しつけ)と表裏一体の関係にあります。たとえば観光に関連する広告の例を見てみましょう。

http://www.hankyu-travel.co.jp/chiiki/event/promotion.php
阪急交通社による、石川県の観光PR広告です。ここでは、「もてなしのいしかわ」という表現とともに、温泉宿でのんびりとした時間を過ごすことができるイメージが画像と文字によって提示されています。その下にはこう書かれています(判読可能な部分のみ抜粋)。
「すべてを忘れさせてくれる雄大な景色、心をほぐす名勝、さりげない気配りが心地よい宿」
ここにおいて石川は、その景色が観光客の「すべてを忘れさせてくれ」るとともに、名勝は「心をほぐ」してくれて、なおかつ「さりげない気配り」によって「心地よい」気持ちにしてくれる宿があなたを迎えてくれるというイメージとともに表現されています。たしかに魅力的ですね。そして、その通りの経験が現地でなされることを期待して観光に訪れる人もいることでしょう。メディアはこのようにして観光地のイメージを構築し、私たちは自覚せずしてそのイメージを実際の観光地に投影し、「期待」と「現実」の差異を測定するのです。この意味で、観光は先入観やステレオタイプと切り離せません。
「田舎の人は暖かい」「おばあの笑顔」「情熱の国イタリア」「エキゾチックなアジア」「南国の青い海と白い砂浜」…観光的な魅力として発信されているステレオタイプには枚挙に暇がありません。
こうしたメディアの構築的側面を自覚し、意識的になることは、観光客として重要な能力かもしれません。私たちが無意識に抱く観光地への期待や欲望は、そのほとんどがメディアによってつくられているのです。メディアが私たちに何を期待させようとし、どのような欲求を抱かせようとしているのか。この広告には何がどのように描かれ、反対に何が描かれていないのか……。メディアは喚起するイメージを読み解くことで、そこでは描かれていない新たな魅力の発見にも繋がるかもしれません。
こうしたメディアを媒介した先入観やステレオタイプに自らが影響されていた(強く言えば、縛られていた)可能性を自覚する契機となるのが、観光地における「ガッカリ」だといえるでしょう。自分がどんなイメージを無意識に抱いていたのか、どんな期待を相手に投影していたのか。それに意識的になることで、ガッカリのショックを和らげたり、あまりに一方的な要求を相手に投げかけてしまっていた可能性に気づいたり、無意識に構築されていた「自分自身の観光のクセ」のようなものを自覚・自己相対化できたりする可能性があります。
旅や観光をつうじて自分自身を知る。「ガッカリ」は、そのきっかけをくれるものだといえるでしょう。
サスタビ外部アドバイザー担当。北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院 専任講師。立教大学大学院観光学研究科 博士課程後期課程修了。博士(観光学)。専門は文化人類学、観光研究、モビリティ研究。北海道札幌市出身。
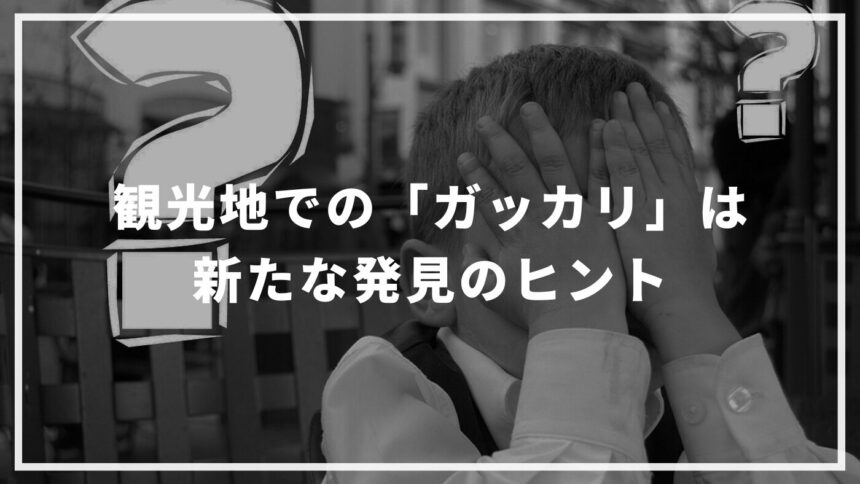

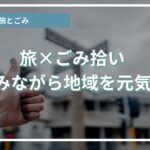

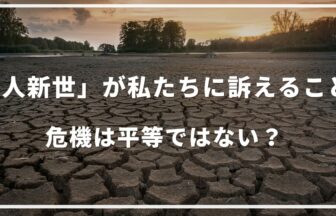

-2-336x216.jpg)



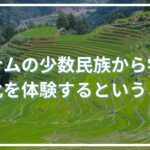


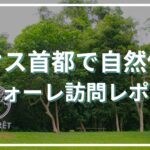
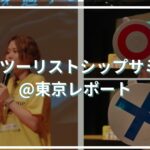
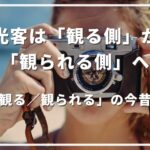






この記事へのコメントはありません。