観光という「イメージのパッケージ」
【前編】では、私たちの日々を構成する行為(食べる、見る、乗る…)がじつは旅の構成要素でもあったことについて、みてきました。観光や旅とは、そうしたありふれた行為の集合体を「目的地への移動」と結びつけたうえで、ひとまとまりに「パッケージ化」したものなのです(門田 2021)。
このパッケージはえてして、旅行会社や観光産業によって準備されてきました。彼らはこの「パッケージ化」を効率的かつ魅力的に商品化してきたといえます。パッケージ・ツアー、すなわちガイドや添乗員のいる団体旅行はこの典型です。乗る、食べる、見る、写真を撮るといった一連の行為は、ガイドやツアー行程の指示通りに実施されていきます。
この記事で「観光のパッケージ化」というときには、上記のパッケージ・ツアーに加えて、もうひとつの含意があります。それは「何をすれば観光なのか」をめぐる、すでに用意された「観光のイメージのパッケージ」という意味です。団体旅行のそれが「行為・行程のパッケージ」だとすれば、後者は「イメージのパッケージ」とでもいえるでしょうか。
あれって観光っぽいよね。これは観光っぽくないよね。うわこの場所すごい観光地っぽいね…そうした評価を私たちは普段からなにげなく行ってきたはずです。
そのようにして、「なんとなく共通理解されている、観光っぽさ(ぽくなさ)」が、「観光のイメージのパッケージ」です。このイメージに沿って観光や旅を計画し、楽しむ観光・旅のあり方を、この記事ではひとまず「パッケージ化された観光」に含めています。したがって、ガイド付きの団体旅行(パッケージ・ツアー)に限らず、たとえ個人旅行や単独での放浪旅行のようなものであっても「イメージのパッケージ」の内側にありえます。
観光や旅は、ほとんどの場合「誰かがすでに楽しんだことの再上演」として営まれている可能性があります。団体旅行は旅行会社や観光産業の準備したツアー行程によって「パッケージ」がつくられていましたが、その「パッケージ」をつくる主体が旅行会社からインスタグラマーに変化しただけかもしれないのです。
ひとりひとりが「旅をつくる」ための想像力
何をすれば観光なのか、何をすれば「旅っぽい」のか。何をすれば楽しいのか…そうした事柄を、すでに「ある」枠組み=パッケージのなかで繰り返すこと。そうした既存の旅や観光のあり方ではなく、ひとりひとりがより自由に、創造的に「旅をつくる」ための方法を考えてみましょう。
もちろん、わたしは「パッケージ」について述べることで、観光者や旅人は踊らされているとか、誰かに従っているだけで自主性が無いとか、そういうことを言いたいわけではありません。また、従来から「ある」旅や観光が悪いということも、全く思っていません。ただし、従来型の観光や旅がその一側面において、何か新しいサステナブルな旅・観光のあり方を要請するようなあり方として存在してきたとするならば、私たちはこれまでとは違う旅・観光のあり方を模索することや、そのための想像力を養う必要があるのだと思われます。
前編を含め、ここまでの整理を経て、2つのことを指摘しておきたいと思います。
ひとつは、観光と、私たちの日常生活上の種々の行動との間に、決定的な違いなどないような気がしてくるという点です。

旅の非日常は、誰かの日常でもある
もちろん、「目的地への移動」という点は大きな要素です。自宅で寝るのと旅館で寝るのとでは大きな違いがあるでしょう。そのようにして旅と日常生活との決定的な差異を探究することも可能です。しかしその「目的地」というのも、近年ではマイクロツーリズムや「近場観光」の登場のなかで、必ずしも遠くの、異郷の、そして自分にとって馴染みのない未踏の場所とは限らなくなっています。
つまり、観光のようにして行為を楽しむ可能性は、どこにでも隠れている可能性があるのです。この事実を「観光的なもの」の遍在、と表現する者もいます(門田 2021)。究極を言ってしまえば、つまらない行為の反復と、観光的な行為とを隔てるのは自分の想像力の程度ですらあるのかもしれません。
そう考えると、観光の可能性はなによりもあなた自身に懸かっている、そんな気がしませんか。
これが2点目です。つまりどんな行為も「観光的」「旅的」にしていくことは不可能ではないということです。「観光的なもの」は遍在しているのであり、むしろ問題はそうして周囲に転がっている「観光的なもの」をどう見いだすことができるか、という点にあるといえるでしょう。
これが、前編から引き続き述べてきた「パッケージの解体」という言葉の意味です。既存の観光のあり方(=パッケージ)にとらわれず、人の数だけの観光のあり方、旅のあり方を、ひとりひとりが「つくる」。それが当たり前になれば、従来の環境負荷を内包してきた観光とは異なる、よりサステナブルであり、かつ「楽しい」旅のあり方がどんどん開拓されうるのではないでしょうか。

ゴミ拾いも、観光になりうるかも
焦点化してみる:旅で、何がしたい?
考えてみれば近年では、「食べる」や「撮る」などのひとつの行為に特化した観光のあり方も登場してきています。
たとえば昨今の感染症対策の一環として政府が提起したのは、農林水産省主導による飲食需要喚起キャンペーン「Go to Eat事業」、経産省主導による興行需要喚起キャンペーン「Go To イベント事業」や商店街振興キャンペーン「Go To 商店街事業」などでした。観光は観光で「Go To トラベル事業」が国交省(観光庁)によって進められましたが、他のGo To事業も観光と密接に関わりながら、何かひとつの行為や場所、目的(食べる、イベントに参加する、商店街に行く…)に焦点化したかたちで実施されてきました。
このようにして、「何かひとつに焦点化する」ことは、「旅・観光の脱パッケージ化」のひとつの方向性だと考えられます。
単に食べたいだけ、発見がしたいだけ、乗り物に乗りたいだけ、誰かとともにいたいだけ、ホテルに泊まりたいだけならば、それぞれの「したい」を別個に、分割してやればいいだけだけのはずだ。いま私たちが観察しているのは、近代とともに生まれた統合型観光が元の個別的要素に分解していくプロセスである(門田 2021:23)
旅をしたい、観光がしたいという漠然とした欲求を抱いたときに、「自分は何がしたいのか」を少しだけ突き詰めてみる。そうすれば、旅や観光の目的が明確化されてくると思います(もちろん、何かひとつ「だけ」に絞らなければならないわけではありません)。
2つのメリット:よりサステナブルな旅へ
旅・観光という大まかな括りのなかで、自分の「やりたい」を明確化してみること。この作業によって、何が起きるでしょうか。そこには、サステナブルな旅や、サステナブルな社会の実現にかかわる2つのメリットが挙げられます。
第一に旅・観光それ自体が、目的から手段へと変化する可能性です。
旅・観光の目的を明確化すれば、目的が「旅・観光すること」から「○○を食べる」「△△に泊まって温泉に入る」といった具体的なものへと、移行していきます。旅・観光それ自体が目的となるのではなく、旅や観光は「手段」になる。つまり、何かを実現し、満たし、達成するための手段としての旅と観光という可能性が浮上してくるのです。
観光や旅は、手段である。その考えは、サステナブルな社会の実現における旅や観光の役割を考えるうえで、重要なヒントになります。旅や観光は、サステナブルな社会をつくっていくための手段にほかならないからです。サステナブルな旅・社会、そしてサステナブルな社会の実現をわたしたちひとりひとりが考えていく際に、旅や観光を目的ではなく手段として考えるという発想はその軸となるものであり、「焦点をあててみる」という試みはその良いトレーニングになると思われます。

2つ目のメリットは、サステナブルな旅と社会をめざすうえでの、より直接的なメリットです。旅・観光の目的ややりたいことが明確になれば、その目的の達成を軸に据えた旅・観光を計画しますよね。その旅はきっと、自己目的化された、漠然とした旅・観光よりもコンパクトなものになると予想されます。コンパクトになるということは、規模が小さくなり、種々の負荷が低減されるということでもあります。旅の最適化ともいえるでしょうか。
また、それは旅の洗練にもつながるのでしょう。「△△△な宿に泊まってみたい」「○○な料理を食べてみたい」というふうに目的が定まれば、それについて、よりフォーカスをあてた情報収集ができるはずです。なんとなくガイドブックや「○○のおすすめスポット8選」といったページを眺めているよりもずっと、ニッチで「深い」情報や旅のスポットを発見できるのではないでしょうか。サステナブルな取り組みをしている宿や食事処、場所や取り組みも、そのようにして焦点化した検索をすればより発見しやすくなるでしょう。
今回は「焦点化する」に注目して、「旅をつくる」のひとつの具体的なヒントを探ってみました。【後編】では、「旅のつくり方」についてもう少し考えてみたいと思います。
参考文献
門田岳久(2021)「遍在化する〈観光〉――フライトシェイム運動から近所の再発見まで」『RT』1巻、pp.16-24. 誌面はこちらから

サスタビ外部アドバイザー担当。北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院 専任講師。立教大学大学院観光学研究科 博士課程後期課程修了。博士(観光学)。専門は文化人類学、観光研究、モビリティ研究。北海道札幌市出身。
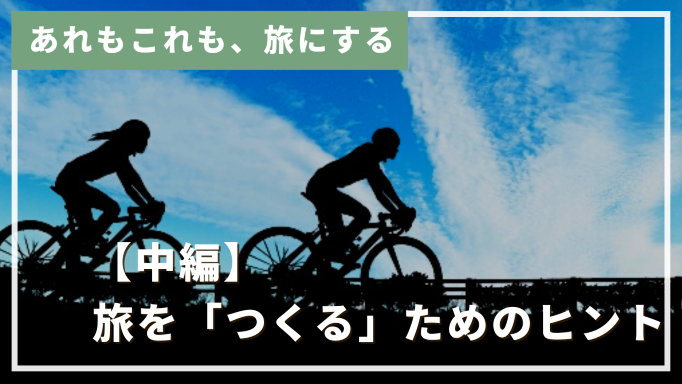



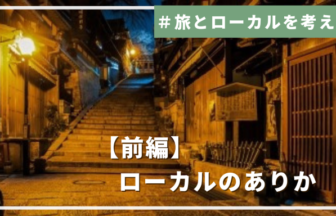
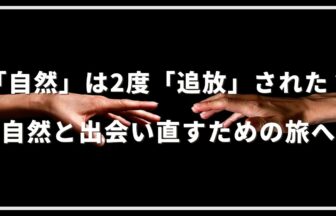
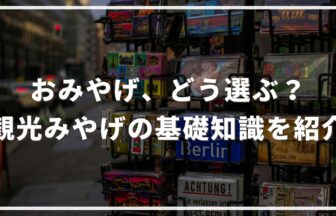

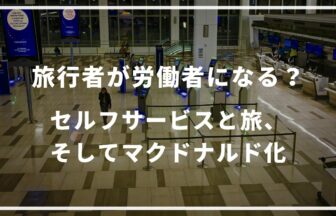




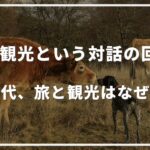




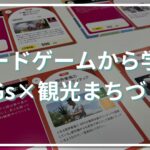




この記事へのコメントはありません。