近年のAI技術やコロナ禍の影響もあって、私たちの生活には「自動化」や「セルフサービス」がますます浸透しています。たとえばレストランでも、機械やスマホで商品を注文でき、ロボットがテーブルまで食品を運んでくれて、さらに無人レジやQRコードで支払いを済ませることもできます。従業員と一切会話をせずに外食をすることすら不可能ではない世界です。
みなさんは、そうしたセルフサービスや自動化の広がりについて、どのような印象をお持ちでしょうか。また旅や観光の場面でもそれらが導入され、広がっていくとしたら、どう思いますか。

「他者との煩わしいコミュニケーションが減って嬉しい」「人との会話が旅の醍醐味なのに味気ない」「外国人でも利用できて利益拡大につながる」「少子高齢社会では必須」「便利になることはよいことだ」「旅や観光から、偶然性やハプニングが無くなり、システマチックなものになってしまう」「人の仕事が奪われる」……などなど、さまざまなシチュエーションや文脈に応じて、それぞれ多様な意見や印象があることだと思います。
今回の記事では、とくに「セルフサービス」が旅や観光の場で広がることについて、「マクドナルド化」や外食産業の展開のお話も補助線にしつつ、少し考えてみたいと思います。とりわけ、人手不足が取りざたされている宿泊業界における、旅人や観光者の「セルフサービス」の可能性や課題についてです。このテーマについては数回の記事で検討していく予定ですので、今回の記事では概要や基礎知識に関わる内容が多くなるかと思います。
マクドナルド化と、効率優先の世界
グローバル化が進む中で世界にくまなく広がったマクドナルド。カリフォルニア州のひとつのハンバーガー・レストランからはじまったその展開を支えていたのは、「マクドナルディズム」とも称される、効率と利益を最大化しつつコストや運営リスクを最小限にとどめる特徴的な「合理化」の仕組みでした(リッツア 1999)。そしてファストフード業界を筆頭にその仕組み自体もまた、「マクドナルド的な経営」「マクドナルド的な働き方」「マクドナルド的な考え方」として世界に広がっていったといえるでしょう。
そうした「マクドナルド化」の詳細については以下に挙げる他のサスタビ記事で詳しくご紹介しています。そちらからご覧になっていただければ理解が深まると思います。
「効率性」と客のコントロール
「マクドナルド化」には、「効率性」「計算可能性」「予測可能性」「制御」という4つの特徴が存在すると考えられています(リッツア 1999)。それぞれについては前掲の記事をご参照していただきたいのですが、今回の記事ではとくに「効率性」に着目したいと思います。
効率性。仕事の効率を高めること。ファストフード店では、その理念が追求されています。従業員の働く内容を簡素化し、細かく分担することで個々の業務を高速化したり、仕事をマニュアル化することでベテランも新人も同じようなパフォーマンスで働くことができる環境を整えたりする工夫が導入されています。
段取りの悪い従業員は、効率の低さのためビッグマックの準備や引き渡しを遅らせる可能性をもっている。規則に従うことを拒否する従業員は、ハンバーガーにピクルスや特製ソースをつけ忘れ、そうすることで予測不可能性を生みだしてしまう。さらに、不注意な従業員はフレンチフライを箱の中に入れる量を間違えて、フレンチフライのLをMにしてしまうかもしれない。以上のようなさまざまな理由から、マクドナルドは、たとえばカップがいっぱいになると自動的に適量で止まるソフトドリンク分配機や、フライがカリカリに揚がると、フライが入ったカゴを油から引き上げるフレンチフライ機、さらにはあらかじめ打ち込みが完了しているプログラムによってレジ係が商品の価格や金額を計算する必要をなくしてあるレジ、そしておそらく将来的には、ハンバーガーを製造するロボットといった非人間的な装置が人間に取って代わる仕組みを着実に押し進めざるをえないと感じている。この技術体系は労働者に対する企業管理を強めるが、このようにマクドナルドが客に保証しているのは、自社の従業員とサービスが不変でありつづけるということである(リッツァ 1999:34-35)
そしてマクドナルドにおいて画期的だったのは、お客自身が商品の受け取りや後片付けをすること、すなわち客が「労働をする」という仕組みを導入したところにあると思います。お金を払い、サービスを享受する主体であるはずの「客=消費者」が、サービスを提供する側の仕事もおこなう「労働者」になること。改めて考えてみると不思議なことだと思いませんか?今回、この「客が労働者になること」にポイントを定めてみたいと思います。

ファミリーレストラン
「客自身にも働かせる」ことによって業務効率や顧客回転率を高めようとする仕組みは、「セルフサービス」とも称されますね。このセルフサービスの仕組みは、日本ではファミリーレストランの展開と深く関わっています。
日本ではじめて生まれたファミリーレストランは、1970年7月にオープンした「すかいらーく」であるとされています(その後ロイヤルホストが1971年12月、デニーズが1974年4月に第1号店が誕生)。ちなみにマクドナルドが日本にオープンしたのは1971年9月で、ミスタードーナツと同時でした(なおケンタッキー・フライド・チキンは1970年11月にオープン)。1970年代は、日本において「外食」のあり方が大きく変容をみせる重要な転換点ということができそうですね。
加島卓は、1970年代から1980年代、そして1990年代にかけてのファミリーレストランの変容について以下のように整理しています(加島 2023:170-175)。
まず1970年代に登場したファミリーレストランは、その「新しさ」や洋風料理の珍しさを家族と一緒に楽しむ場として捉えられており、快適で魅力的な店内レイアウトや、料理の味と価格、しっかりとしたサービスが重要視されていたといいます。その後1980年代では、ファミリーレストランの多様化が進み、店ごとの個性やエンターテイメント性、メニューの多様性が高まりました。また24時間営業も増え、「家族で楽しむ場」から、主婦や若者グループなど「様々なグループが楽しむ場」となっていきます。他方、コンビニエンスストアも急増した1990年代になると、低価格でヴァリエーションに富んだ食事を提供するファミリーレストランが急展開していきました。ファミリーレストランは「ぜいたく」ではなく、気軽で身近な場所となったのがこの時代です。
「1990年代のファミリーレストランは家族や友人と一緒でなくても、一人で満足できるコストパフォーマンスの良い場所になったのである」(加島 2023:172)。
セルフサービスの展開
以上の展開のなかで、1990年代以降のファミリーレストランに「セルフサービス」が導入されていきます。「空いているお好きな席にどうぞ」という今では慣れ親しんだ声かけや、おしぼりや水のセルフサービスはこの時期の発明品といえます。
「これまでのファミリーレストランはさまざまなサービスを店員に提供してもらう受動的な空間だったが、セルフサービスを導入した1990年代のファミリーレストランはお客がサービスの一部を担うという意味で能動的な空間になりはじめたのである」(加島 2023:174)。
カトラリーがあらかじめひとまとめになってテーブル上の籠に入れられていることや、「ドリンクバー」が導入され、店員よりも客のほうが店内をたち歩いているような光景は、それ以前では「当たり前」ではなかったのです。
当初のファミリーレストランは、「ぜいたく」な場所であり、お金を払って、お店側のサービスを享受しながら家族団らんを楽しむ場であったといえます。それが次第に、より低価格・高効率で手軽に時間を過ごす場所として広がっていったとみることができます。その転換のなかで、セルフサービスの要素も増えていきました。

客自身が働くことをどう捉える?
先に述べたようにマクドナルドは、「客自身に働かせる」セルフサービスの仕組みを初期から実施してきました。注文した商品を自分で取りに行ったり、食後のハンバーガーの包装紙や紙コップを自分で分類し片づけたり。それによって配膳や清掃のスタッフを減らし、その分レジや調理などに人員を配置し、業務や顧客回転率をスピードアップさせてきました。
客、すなわち消費者やサービスの利用者が、労働者にもなる。セルフサービスの「消費者が労働者になる」その仕組みについて、つぎは旅や観光の場面で考えてみたいと思います。
人手不足の問題
昨今の観光産業、とくに宿泊業界では、人手不足が問題視されています。少子高齢化や労働環境の問題など、潜在的にこれまで蓄積してきたものが、新型コロナウイルス感染症の影響を経て顕在化している状況です。日本総研の発表する2022年の記事「観光業の人手不足の現状と課題」(藤山2022)では、以下のように述べられています。
宿泊業・飲食サービス業では、コロナ禍以前から、休日・休暇の少なさや賃金水準の低さが雇用面の課題となってきたほか、労働環境の厳しさや非正規雇用の多さなどを背景に、離職率が高い傾向にあった。さらに、宿泊業では、労働者の高齢化が進んでいるほか、コロナ禍で産業としての安定性や将来性への懸念が強まっており、今後人手不足が一段と深刻化する恐れがある。
そしてその解決・改善にむけて、旅行商品の高付加価値化に加えて、「①デジタル化・DXによる労働生産性の向上、②雇用の安定、③地域一体となった取り組み、④国や地方自治体の支援」が必要であると指摘されています。①は、たとえば無人チェックイン機器を用いたチェックインの自動化などがすぐに思い浮かびますね。

旅人による「思いやり」
旅行業界における人手不足の背景を踏まえて、できるかぎり宿やお店に迷惑や不必要な手間をかけさせないよう、自らの旅行の仕方に気を配ろうとする意識も高まりつつあるといえます。Booking.comが2024年度版として実施・公開した「「サステナブル・トラベル」に関する意識調査」(世界34か国・地域、3万人以上が対象)では、世界中の旅行者のうち75%が「今後12か月のあいだによりサステナブルな旅行をしたい」と考えていると明らかにされました。また「訪れた場所について、到着したときよりも良い状態で旅行先を後にしたい」と回答したのは全世界の旅行者で71%(日本人の旅行者は56%)でした。
宿泊したホテルをキレイに使うことや、出たゴミを分別すること、トイレットペーパーは使いかけのものから使うといったことなど、旅行者の側がホテル側のことを考えて行動する例もあるといいます。またアメニティをなるべく使用せず、持参した歯ブラシやクシなどを使うことを意識している旅行者もいるでしょう。サスタビでも、「サスタビ20ヶ条」のなかで「06 マイボトルやカトラリーを持参しよう」「07 アメニティも持っていこう」「14 節電や節水に気を付けよう」といった旅行者側ができる配慮について情報発信をしています。
- 「06 マイボトルやカトラリーを持参しよう」
- 「07 アメニティも持っていこう」
- 「14 節電や節水に気を付けよう」
- ※また、「アメニティ」についてはコチラの記事もご参照ください→「脱「もらってばかりの旅人」宣言!アメニティと観光をめぐる豆知識」
旅行者の側からすすんでできることをし、環境やホテル/宿にできることをしようとする意識は、「サステナブルな旅」を実践するうえで重要なものだと思われます。また「エコプラン」など、たとえばベッドシーツの交換をしない、部屋の清掃を不要にすることで宿泊代金を割り引くようなサービス・プランも実際に存在しています。付け加えれば、チェックインしたあと部屋着やアメニティを自分でロビーで取り、部屋までもっていくといったことは一部のビジネスホテルを中心にスタンダードとなりつつあります。
マクドナルド化か、それとも?
旅人側が自ら動いたり、不要なサービスを断ったりすることをつうじてホテルや環境に対して配慮や貢献をする。そうした取り組みの一環としてセルフサービスやエコプランを理解することは不可能ではありません。他方で、「客の側が自ら働く」という仕組み・構造という点では、そうした旅人側の「思いやり」は、もしかするとマクドナルド化の効率性の論理とも無関係ではないのかもしれません。配慮なのか、それとも効率化の徹底なのか。これはおそらく二者択一で考えることはできない複雑な論点です。
マクドナルド化は、労働者の労働・雇用環境を不安定にさせたり、環境に悪影響をもたらしたり、労働者を「交換可能」なロボットのように主体化させたりする危険性をもつと指摘されてきました。たとえば「マクドナルド化」について、冒頭で紹介したジョージ・リッツァは、その合理化を追求した仕組みが不可避的に「大量の非合理性」をも生み出してしまうといいます。
ここでの基本的発想は、合理的システムはかならず大量の非合理的な結果を生みだすというものである。これに対するもうひとつの言い方は、合理的なシステムは人間理性を否定する、つまり合理的システムはしばしば道理に適わないということである。
たとえば、マクドナルド化は環境に対するマイナスの効果をあれこれと生みだしている。一つの例を取り上げてみよう。人びとがファストフード・レストランで出てくるのを楽しみに待っている予想通りのフレンチフライをつくるためには、形のそろったジャガイモを育てる必要がある。それによって明らかになるのは、そうしたジャガイモを育てる必要がアメリカ北西部の生態系に重要な影響を与えているということである。そのようなジャガイモを生産する巨大ないくつかの農場は、いまや化学薬品を大量に使用している(リッツァ 1999:38)。

マクドナルドというひとつの店舗、あるいはシステムの合理性や効率性だけを考えるのではなく、それを地球の環境問題のなかに位置づけて考えると、別の非合理性の問題が見えてくるということですね。また、リッツアは労働の問題にも言及しています。
ファストフード・レストランがもたらすもうひとつの非合理的な影響とは、食事をする場所や作業をする場所がまったく脱人間的な環境に頻繁に変わっていくということである。ハンバーガーを求めて一列に並んでいる客たちやドライブスルーのラインに並んで待っている客たち、そして食品をつくっている従業員たちがしばしば感じているのは、自分自身が作業ラインの一部になっているという感覚である(リッツァ1999:38-39)
こうした点を考えると、宿泊産業における労働やサービスの「合理化」についても、多角的にそして慎重に考えていく必要性が浮かんでくるように思います。便利になったり、スムーズにチェックインできるようになったりすることはもちろん嬉しいことでもあり、また業界における人手不足の問題も深刻です。他方で、利益や効率性だけが重視された仕組みがもし「サステナブル」「エコ」といった言葉とともに進展していくことがあるとすれば、それはまた問題を含んでいるようにも思われます。「客が働く」という点は旅行業界においてはなかなか複雑な問題ですね。
マクドナルド化が、あるいは「旅人が働くこと」が「善」なのか「悪」なのか、それはわかりません。宿やスタッフのために旅人自身ができることをしたり不要な手間や資源のロスを生まないように気を付けたりする、こういってよければ「旅人主体」の「サステナブル中心」の取り組みや試みが進んでいくこともあれば、「企業主体」で「利益効率中心」の価値観のもとで「客が働く」仕組みがつくられていく側面もおそらくあります。これもまた二者択一ではなく、旅人と企業の双方が「サステナブルな社会」や「持続可能な観光」の進展という同じ方向に向かって動いていくことができるような道の模索を続けていく必要があるでしょう。
このテーマについては引き続き検討をしてみたいと思います。
参考文献・HP
- 加島卓「外食」高野光平・加島卓・飯田豊編『新版 現代文化への社会学:90年代と「いま」を比較する』北樹出版、pp.169-178。
- 藤山光雄2022「観光業の人手不足の現状と課題(リサーチ・フォーカスNo.2022-049)」日本総研『経済・政策レポート』2022年12月15日(https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=104101, 2024年9月2日確認)
- Booking.com Japan K.K. 2024「ブッキング・ドットコム、2024年版「サステナブル・トラベル」に関する調査結果を発表」PR TIMES 2024年6月25日(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/15916, 2024年9月2日確認)
- リッツァ・G 1999『マクドナルド化する社会』正岡寛司監訳、早稲田大学出版部。
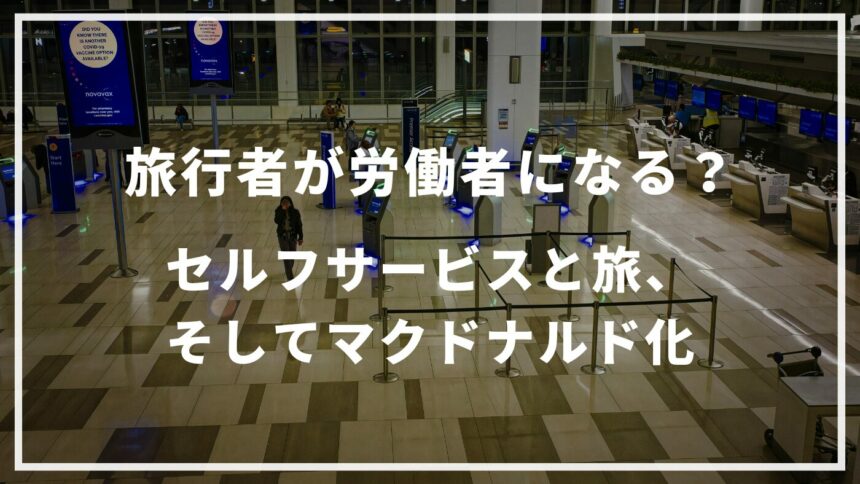

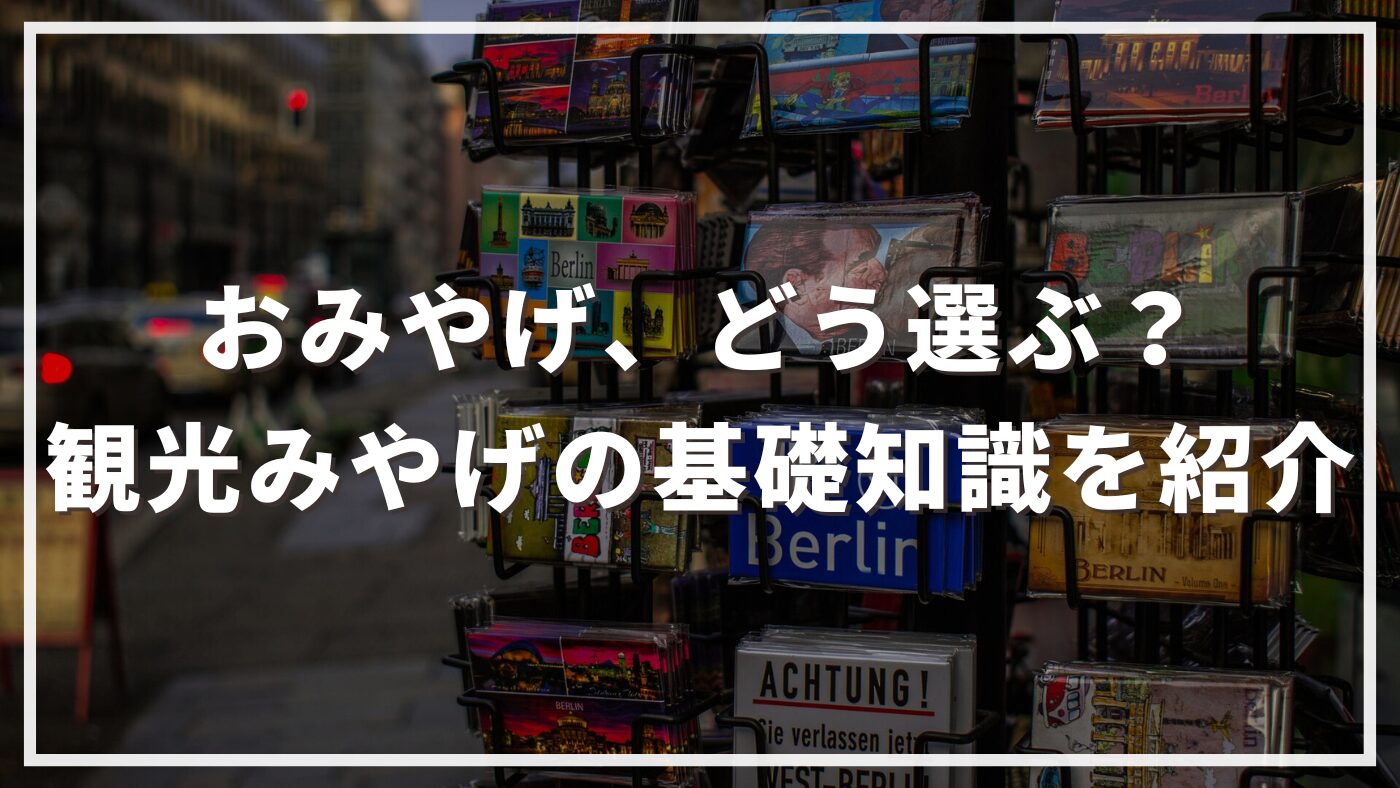



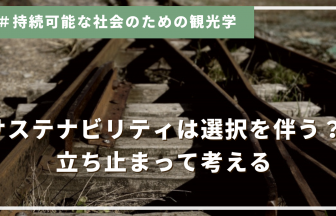


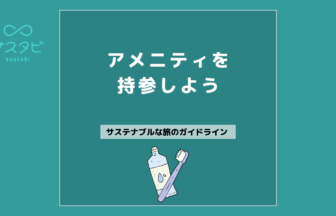



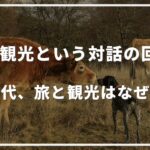



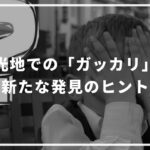
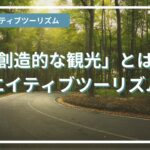
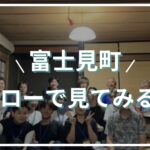



この記事へのコメントはありません。