あなたは旅人?それとも観光客?
突然ですが、旅人と観光客(者)の違いはどのようなものでしょうか。
どこか遠くの地から突然やってきて、少しの間滞在し、風と共にまたどこかへと旅立っていく人たち。旅人には、そのようなイメージがあるかもしれません。彼らは到着地をまた出発地として、次から次へと移動=旅をつづけていきます。
対して観光客の場合、出発地から目的地へと至り、その後再び出発地へと戻っていくという「円運動」に特徴が置かれることが多いように思います。転々と点を結ぶように移動を進めていく旅人と、どこかへ行ったのちに帰ってくる観光者の往還。
そうした「移動の軌跡」のほかにも、両者には違いがありそうです。たとえば旅人の旅には、挑戦的であるとか、自分の意志で旅路を決める(けれども成り行きに身を任せる)とか、利便性に頼らないなどの意味づけが付されることが多い印象です。不確実性があり、主体性があり、ある種の「冒険性」がある、それが旅だと。
これに対して観光者の移動の場合は、それがツアーとして組織されている(計画的/組織的)ことや、商業的であること、安全性や利便性あること、といった点に特徴があると言えるかもしれません。観光(ツーリズム)とはそもそも「近代」以降に生じたものであり、したがって近代性という特徴が、それ以前から存在していたであろう旅から観光を区別するものなのだという見立ては、ひとつ有効な説明だと思います。
自分のことを「観光客」ではなく「旅人」と名乗り、自分の移動を「観光」ではなく「旅」だと敢えて呼んだ経験がある人は、もしかしたら少なくないかもしれません。

「ヨソ者」としての観光者/旅人
さて、そうして異なる意味合いを付与され、さまざまに使い分けられている観光客と旅人ですが、両者にはもちろん共通点もあります。それは端的に言えば、どちらも「ヨソ者」であるということです。
地域には、そこで生まれ育ったり移住してきたりを経て長らくその場所で暮らしてきた人たちの共同体=コミュニティが存在します。そして、その場所で生活する人は、「自分はこの地域の住民である」「地域の一員である」という意識を多かれ少なかれ抱いていることでしょう。
旅人や観光客はとうぜん、旅や観光で訪れる地域のメンバーではありません。彼らはどこか別の場所=ヨソから、一定期間の間だけ地域に滞在し、その後どこかへ去って行ってしまう存在です。また来てくれるかどうかすら、不透明です。
地域の「外部者=ヨソ者」。この位置づけは重い意味を持ちます。もちろん観光者や旅人は一時的には地域の「ウチ」に足を踏み入れ、経済的に貢献したり、文化的な交流をしたりすることができます。しかしそれでもなお彼らは「この地域」「わたしの地域」に住み着いてくれることはなく、いつか必ず地域から立ち去りゆくことが刻印されている存在なのです。地域の「ウチ」に完全に入ることはない、内部と外部の狭間にあり続ける存在が、観光者や旅人を特徴づけています。
地域の問題に向き合うべき人々は、地域の「ウチ側」だけ?
地域の外部にいること、そして、たとえ内部に一時的に入ったとしても、すぐに出て行ってしまうこと。この刹那的で流動的な特徴は、地域が抱える諸問題からも観光客や旅人を外部化してきました。
地域創生や地域の課題解決において観光者や旅人は非常に重要視されていますが、その多くは彼らの経済的な貢献に焦点化されています。地域の問題に向き合い解決をしていくべきはやはり地域の内側にいる行政や市民である、という見方は根強く、したがって観光者や旅人はそのウチ側の取り組みに対する間接的な支援としての経済的貢献を期待されてきたと言うことはできるかと思います。

また、観光の盛り上がりによって地域住民が地域への愛着を高めたり、地域の文化継承を活性化させたりすることも期待されていますが、そこでも観光者や旅人は「きっかけ」にすぎず、最終的な目的は「地域住民が」愛着や意識高揚を経て地域活性化に一層奮闘することに置かれているように思われます。
まとめれば、観光者や旅人は経済的・文化的・社会的に「地域に元気を与える」ことが期待されてはいるものの、彼らの外部性(一時性)ゆえに、あくまでその役割は「地域課題に向き合うべき主役としての地域住民」を支援する間接的なものに留められてきたのだと考えられます。
旅人や観光客は、地域の主役になることもできる
こうした現状を踏まえて、観光研究や政策の領域では、観光客や旅人をいかに本当の意味で「地域のウチ」に迎え入れることができるかという点が模索されつつあります。つまり「お金を落とす存在」としての観光客や旅人から、「地域の問題に地域住民と一緒に向き合う存在」としての観光客や旅人への転換の可能性です。そうした検討は、リピーターや関係人口の議論などをはじめとして広がってきています。
たとえば関係人口とは、地域に住み着く「定住人口」でもなく、ただ単に観光に来た一時的なだけの存在である「交流人口」でもない、地域との新たなかかわり方としての可能性が込められた概念です。
こちらも参考になります。関係人口ポータルサイト→https://www.soumu.go.jp/kankeijinkou/about/index.html
観光客や旅人の意識から観光/旅をつくりかえる
関係人口ポータルサイトの発想のように、地域側や地域づくりの政策的側面からは、地域の外部者の問題が刷新されつつあるように思います。一方で、旅人や観光客自身の意識はどうでしょうか。
観光は遊びだから。息抜きだから。旅は自分の成長のためだから……観光や旅は、当然ですが余暇活動や自己成長として意味づけられつづけてきました。逆に言えば、地域づくりに参与することや地域の課題に協力すること、地域とともに課題に向き合うことといった事柄は、観光や旅の目的・意味から除外されつづけてきたのではないでしょうか。
観光者や旅人を地域から外部化してきたのは、もしかすると観光者や旅人自身だったのかもしれません。観光者や旅人自身が、観光や旅を地域づくりや地域協力から遠ざけて、一時的な楽しみのための活動として自らを地域のヨソに置いてきたのかもしれません。遊びだから……一時的な息抜きだから……(地域のお手伝いよりも、もっと楽しいことをしたい)。
旅はとりわけ「自分に向き合うもの」あるいは「自然と対峙するもの」であり、地域に向き合うものではなかったのかもしれません。

「旅」の画像を探すと、自然に立ち向かう者の表象が目立ちます
そうした可能性を踏まえると、旅や観光それ自体のひとつの目的として地域づくりへの参与を再設定することの重要性が感じられてきます。ボランティアに参加することや、「おてつたび」(https://otetsutabi.com/)のような観光、地域を支える「ポジティブ・サステナビリティ」の実践としての旅。

観光や旅で「わざわざ」ボランティアや地域貢献をするのではなく、観光や旅「だからこそ」それをする。そうしたマインドの転換は、サステナブルな旅の新たな道筋を描くように思います。純粋な楽しみだけの旅や観光(それはもちろんあって良いし、それ自体大事なものです)だけではない、新しい旅や観光のあり方へ。たとえ一時的な滞在だとして
働くこと、遊ぶこと、生きること
こんにちでは広く知られている、ワーケーション(workcation/worcation)。みなさんはワーケーションをしたことはありますか?
「パソコンと電源さえあれば仕事ができる」。そんな仕事は増えているように思います。そしてここ数年におけるテレワークの急拡大は、地理的・空間的な制約から仕事が切り離されていくプロセスとして理解できるでしょう。”働き方”をめぐる時空間の変容です。

こんにちと比較する限りにおいて、かつての「仕事」「労働」という活動の領域は明確なものだったかもしれません。仕事は会社でするもの、何時から何時までするもの、というように時間と空間が比較的明確に定められていました。つまり「職場」というハッキリとした労働の時空間があったのです(もちろん、もともと時空間の概念と離れて存在していた仕事/労働もあります。また、たとえば「家事」をどう捉えるかといった問題もあります)。
こうして労働と余暇を区別するのはいわゆる近代的なものの考え方の特徴であり、それは労働とは異なるものとしての余暇と、その時間の過ごし方としての観光の成立に深く関わっています。観光が近代に特有の現象であると言われる所以は、そのあたりにあります。
そうして仕事や労働が場所や時間から解き放たれ、仕事・労働としての独立性がぼやけてくると、当然それらは他の領域と混ざり合っていきます。たとえば日常と労働が結びついて、いま私たちは「夜なのにテレワークしなければならない…」と嘆いています。そしてかつては労働や仕事とは離れた位置にあったとされる「遊び」と結びついて生じてきたのがワーケーションなのでしょう(そう考えると、私たちはワーケーションを喜んで受け入れているのか、それとも「旅行に行ってまで仕事から解放されない」という気持ちで否応なく受け入れているのか、よくわからなくなってきますね……)。
仕事の時空間の変容は、仕事の経験(=どう働くか)そのものまで変容させつつあります。

「なぜここまで“働くこと”が私たちの主要な関心事となっているのか」という問いからワーケーションを考えることも可能です。2000年代以降の労働力不足の問題や、仕事における男女共同参画の文脈などを背景として、働き方について考えることが生活の仕方や“生き方”を考えることと重なり合ってきており、そのことが当たり前になってきているような印象があります。ワーケーションを考えるうえでは、働くことと生きることをめぐる昨今の社会的な認識の変化もまた無視できないでしょう。
さて、そうした小難しい話はここまでとしておき、今回の記事ではこのワーケーションについて基本的な理解を深めつつ、これまでは語られてこなかった「もうひとつのワーケーション」とそのサステナブルな可能性について考えてみたいと思います。
ワーケーションはもともと否定的に議論されていた!?
ワーケーションの概念は、2000年ごろに欧米から発せられてきたと言われています。しかし欧米におけるワーケーションの議論は、仕事と余暇の概念が混ざり合うことへの懸念や否定的見解が主導的でした。これは日本におけるワーケーションのプロモーションをみるに、意外に思われる方が多いと思います。
Brigitta Pecsekという研究者が著した「休日に働くこと(Working on holiday)」という論文では、かつては「8時間睡眠、8時間労働、8時間余暇」であった近代的な1日の生活区分が、情報通信技術の展開によってあいまいになっているといいます。そして、300名をこえる調査対象者の分析から、ワーケーションによる仕事と余暇の合体が、仕事と余暇両方の楽しみや効率を損なう可能性があると指摘しました(Pecsek 2018)。
楽しむにも楽しみきれず、仕事をするにも集中しきれず、ということで結局それぞれを別々に実施した方がストレスが少ない。そう言われると、確かにそのような気もしてきます。

日本におけるワーケーション:欧米と異なる意味合い
それに対して日本におけるワーケーションは、欧米圏よりもやや肯定的に議論されてきました。ワーケーションには地域社会、地域の関連事業者、ワーケーションをする個人、ワーケーションを市場で売る企業という4者を結びつけ、経済的・社会的な地域活性化につながるという期待が込められているのです(田中・石山 2020)。
欧米圏におけるワーケーションの議論は、観光と仕事それぞれの効率性について、すなわちワーケーションを行う個人の問題に注目していたのに対して、日本におけるワーケーションは地域活性化や関係人口の増加など「地域づくり」という幅広い文脈で議論されてきたといいます(田中・石山2020)。
そもそもこれまでは仕事をする場所は日々通う「職場」あるいは自宅であり、生活圏ではない地域に足を運ぶ機会は出張に限られていたかと思います。仕事の文脈で地域に移動し、そこでお金を落としたり地域の人びとと交流したりする機会は、その選択肢すら無かったのです。ワーケーションは、たとえ仕事が目的であっても「どこかの地域に行く」という選択肢を可能にしたといえます。
地域側から見れば、これまでは観光・出張に限られていた来訪者による経済的・社会的メリットが、仕事においても見込めるようになったということですね。

そうしたことから、ワーケーションは地域との関わり方をめぐる多様な選択肢のひとつとして、サステナブルな地域社会づくりのひとつの手段だと考えられそうです。また言うまでもないですが、旅において気を付けるべきこと、守るべきマナーはワーケーションにおいても意識されなければなりません。そのうえで、旅であれ観光であれ仕事であれ、どこかの地域や施設を訪れた際には、なにか自分にできそうなサステナブルな取り組みを探してみること、実践してみることが大切だと言えるかもしれません。
次回の記事では、この点について、もう少し深堀りしてみたいと思います。次回のポイントは、ワーケーションはその目的をハッキリと切り分けることができない(旅でもあり仕事でもある)という点です。ここから、これまでの旅の目的のあり方、そして「もうひとつのワーケーション」の可能性について検討します。
【参考文献】
田中敦・石山恒貴(2020)「日本型ワーケーションの効果と課題――定義と分類、およびステークホルダーへの影響」『日本国際観光学会論文集』(27):113-122.
Pecsek, Brigitta (2018). “Working on holiday: The theory and practice of workcation.” Balkans Journal of Emerging Trends in Social Sciences. 1:1-13.
も、もっと地域の「ウチ」において、地域「とともに」課題に向き合えるような旅/観光のあり方へ。その可能性はまだまだ未踏でしょう。
その模索のために必要なのは、地域が抱える諸問題(人口問題、人手不足、etc.)を旅の中で「他人事」ではなく「自分事」にしていく態度かもしれません。「数日しか滞在しないし…」という気持ちで地域の現状を他人事のようにしたり、見て見ぬふりをしたりするのではなく、「数日しかいられないけどできることをしよう」という気持ちで向き合ってみる。そんな気持ちの切り替えが大切になってくると思います。
次の旅では、自分ではなく地域に向き合ってみませんか?
具体例として、こちらの記事もぜひ!
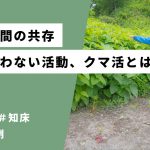


サスタビ外部アドバイザー担当。北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院 専任講師。立教大学大学院観光学研究科 博士課程後期課程修了。博士(観光学)。専門は文化人類学、観光研究、モビリティ研究。北海道札幌市出身。


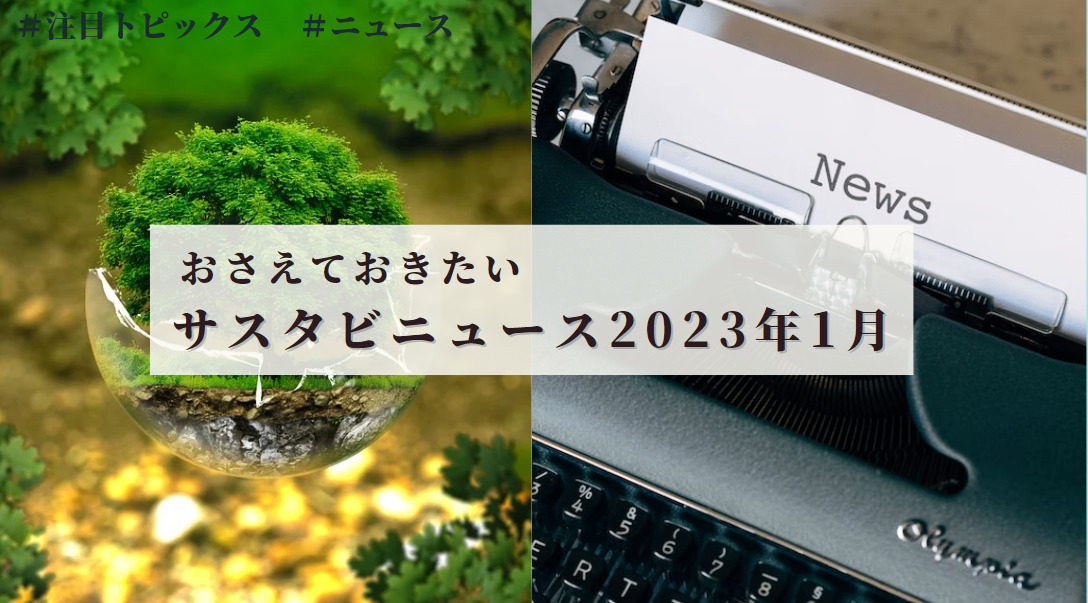
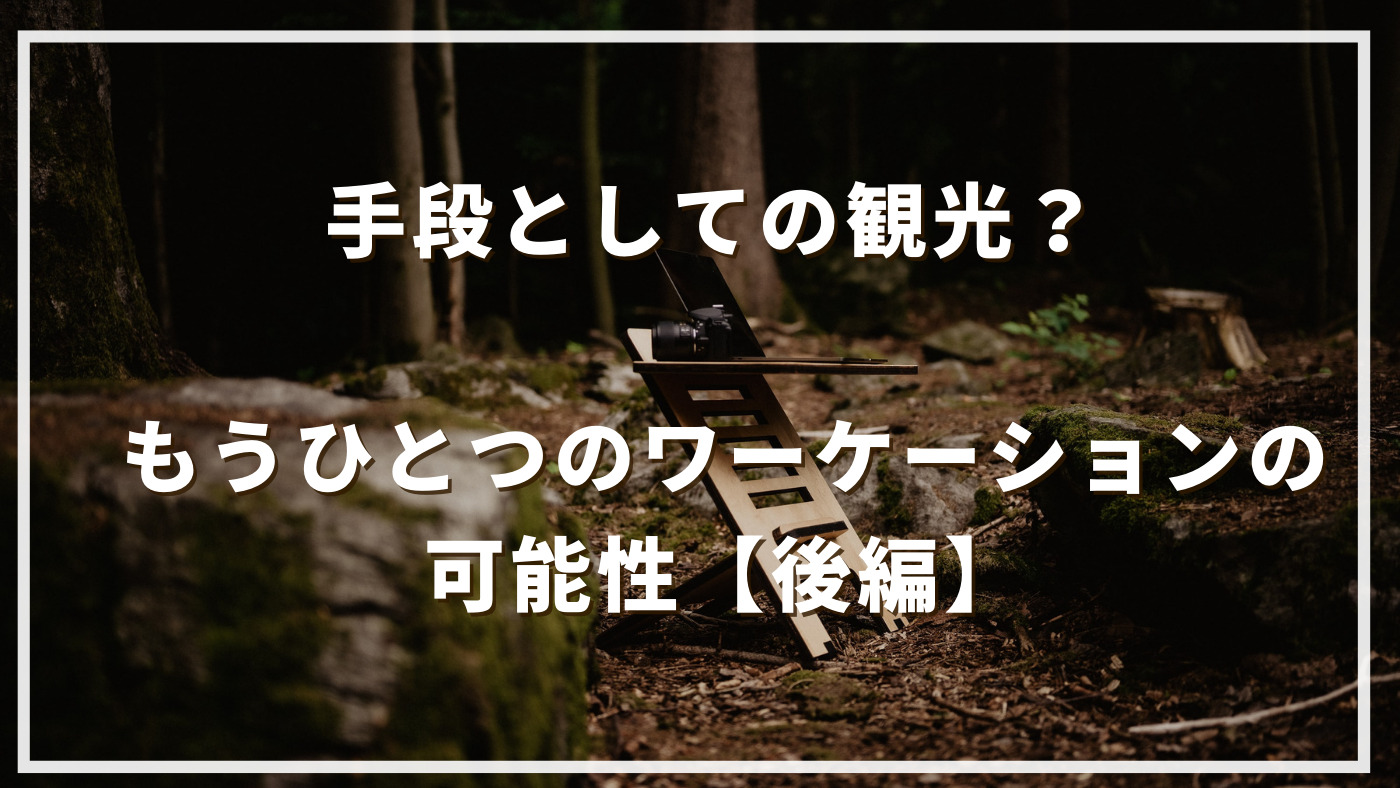


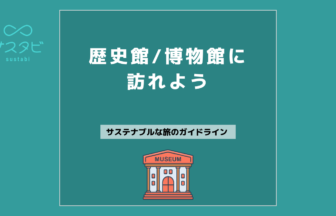

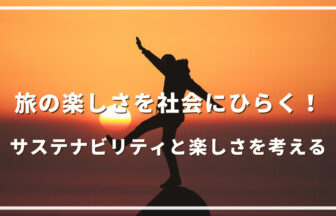
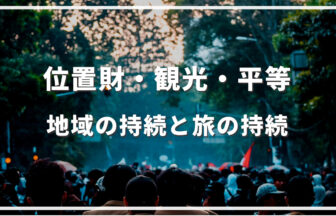



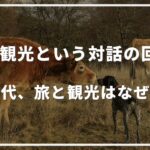


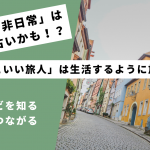
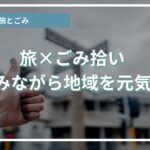

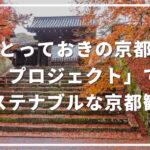



この記事へのコメントはありません。