「位置財」
「位置財」という言葉をご存知でしょうか。日常生活ではほとんど耳にすることのないこの言葉。これは「positional goods」が訳されたものです。
この言葉が言いあらわそうとしているのは、「位置とは、限られたものであり、それをめぐる競争がつねに生じているのだ」ということです。Social Limits to Growthという書籍(邦訳『成長の社会的限界』都留重人監訳、日本経済新聞社、1980年)を著したフレッド・ハーシュが述べるのは、社会に生きる人々がみな最大限の自由にもとづいて行動や消費をしてしまうと、結果的に社会全員の選択の自由が損なわれてしまうような経済の領域があるということです(コモンズの悲劇と似ていますね)。
「位置」。これを少しわかりやすくするために、いくつか例を挙げてみましょう。もっとも簡単なのは、「イス」の例です。電車でもオフィスでも学校の座席でも構いませんが、「すでに誰かが座っている場合、他の人はその椅子には座ることができない」ですよね。その椅子という「位置」は一度誰かが座ってしまうと、その人が離席するまで他のひとは座れません。どこかで空くのを待ったり、別の席に座るしかないですね。

同じ「位置」を同時に占めることができる人数が限られていること。そこがポイントです。位置というものは、本質的に排他的な性格をもっているといえます。
「位置をめぐる競争」(positional competition)
そしてなぜこの「位置」に「財」という言葉がつくのか、それは、「位置」には価値があるからです。また、その価値をめぐって競争が生じるからです。
この点でわかりやすいのは「順位」です。試験やレース、営業成績など、あらゆる競争にいえますが、基本的には1位や2位、3位といった順位はそれぞれ「誰か一人」に与えられますね。「優勝」とか「1位」「最優秀賞」などの順位は、先ほどの「イス」と同じく、みんなで同時に分け与えることができません。それは競争のうえで勝ち取られるものであり、ゆえに価値が付与されます。
1月から2月にかけて日本でもっとも大きな関心の的になる、入学試験。これも位置財の典型例です。誰もがその大学に入りたいと思っても、そこには定員があります。限られた人数しか入学できません。それはイス取りゲームであり、誰かが座るたびに別の誰かが座れなくなっていきます。スポーツのレギュラーや会社のポスト、電車の座席なども、ある意味同じ競争の対象であり、結果です。同じ位置を全員が占めることはできません。
すなわち「位置」は「財(goods)」であり、争われるものであり、そこに価値の優位性が生じます。このことを英語でpositional competition、すなわち「位置をめぐる競争」といいます。

ステータスとしての価値
この「位置財」は、いわゆる「ステータス」の競争とも関係しています。たとえばブランド商品は、それ自体に価値があるかは別として、少数の限られた人しか利用・購入できないということに価値が置かれている側面があります。「そのブランドのバッグを所有している私」「あの車に乗っている自分」といった自らのステータスと結びついた価値観は、そのブランドや商品を誰もが所有できるようになった場合には維持できなくなるでしょう。
ステータスという言葉は、地位、すなわち自分が占めるポジション=位置に関わる言葉ですね。そしてそのステータスの多くは絶対的なものではなく、他者との比較によって価値を帯びることがほとんどです。限られていること、少数であること、そのような希少で競争性の高いものを自分が保有していること(他の多くの人は持っていないこと)。そのようなことに価値を感じる人は少なくないはず。
この例の場合、イスのように物理的に複数人が同じ「位置」を占めることができないわけではありませんが、限られた「位置」を占める人が増えれば増えるほどその「位置の価値」が減じていくという点で、位置は争われるものであり、むしろ「争われなければ意味がない」ものとなっています。

チェス。それはある意味で「位置」の取り合いです。
「位置財」としての観光
観光学の重要な研究者であるジョン・アーリは、観光もまた「位置財」であると、彼の著書『観光のまなざし』(増補改訂版、ヨーナス・ラースンとの共著、加太宏邦訳、法政大学出版会、2014年)の第9章「リスクと未来」で論じています。
観光地や地域には物理的にもキャパシティがあります。そして、どんなにそこが魅力的な場所であったとしても、一定以上の観光者が同時にそこに押し寄せてしまうと、その場所ではさまざまな問題が起きて環境や社会を消耗させてしまいます。
オーバーツーリズムの問題は、まさに「位置財」の話であることがわかります。多くの人がその場所に観光に行きたいと思っても、同時に来訪できる人数や規模は限られている。そのキャパシティを無視して個人が自由に来訪してしまうと、様々な限界問題が生じて、観光地や地域の価値が損なわれてしまうのです。
観光と平等はジレンマに?
すなわち、誰もが自由に、かつ平等に同じ場所に行くことができるようになるという状況は、オーバーツーリズムと表裏一体の関係にあるといえます。観光客を魅了し惹きつけるようなスポット。「この聖なるスポットが位置財となるのだが、この財は観光の平等化によって破壊されていく」(Walter 1982:302)のです。

「観光の平等化」が、観光地を破壊しうるということ。これは大変興味深い指摘です。「観光と平等」をめぐる、このジレンマを考えるべきときが来ていると思われます。観光や旅が平等であることは、おそらく望ましいものだと言えるでしょう。観光や旅をしたいという欲求は、妨げられるべきものではないと思われます。
他方で、すべての人がある程度の自由に行先を選択し、行きたいところに行くことができるという状況がオーバーツーリズムと関わってきたことも、忘れるわけにはいきません。多くの観光客が集まっている場合には、行く時期を遅らせたり、あるいはその場所に行くことをいったん諦めて別の場所に行ったりすることが、おそらく現実的には必要となります。すでにイスに人が座っているならば、順番を待たなければならない、というわけです。
自由。そして平等。民主主義の軸をなすこれらの価値観や概念と、持続可能性(サステナビリティ)をどうセットで考えていくことができるでしょうか。オーバーツーリズムの対策や持続可能な観光の仕組みづくりは、一側面では、観光者や旅人の自由に一定の制限を課す方向性を備えています。入場規制などの直接的なものから、分散への呼びかけなどの間接的なものもあります。もちろん、それらを不平等や不自由の増大と理解することはあまりに早急であり、むしろ自由や平等や民主主義は、完全な自由や平等によっては達成されないのだと考えておくべきものでしょう。モラルや分別をも見失うような自由の道はおそらく荒廃に続いています。
旅人や観光者を増やすことと、観光地や地域を観光の弊害から守っていくこと。持続可能な旅/観光の問題とは、その2つの事柄を同時に目指していく方法をめぐる問題にほかならないのです。今回の記事では、自由や平等といった「大きなテーマ」を持ち出してみましたが、ときには大局観で、腰を据えて、観光/旅とそうした問題を根っこから考えてみることも有意義でしょう。
参考文献
- アーリ・ジョン、ヨーナス・ラースン(2014)『観光のまなざし 増補改訂版』加太宏邦訳、法政大学出版会。
- ハーシュ、F. (1980)『成長の社会的限界』都留重人監訳、日本経済新聞社。
- Walter, J. A. (1982). Social Limits to Tourism. Leisure Studies, 1 (3): 295-304.

サスタビ外部アドバイザー担当。北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院 専任講師。立教大学大学院観光学研究科 博士課程後期課程修了。博士(観光学)。専門は文化人類学、観光研究、モビリティ研究。北海道札幌市出身。
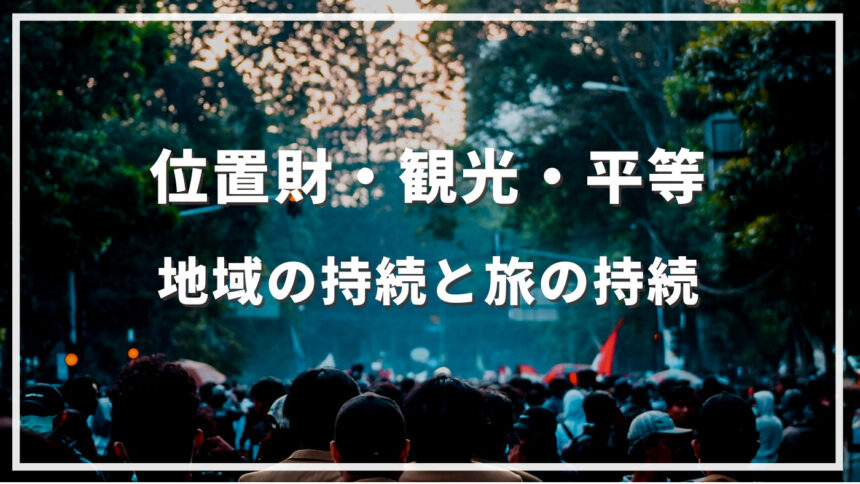

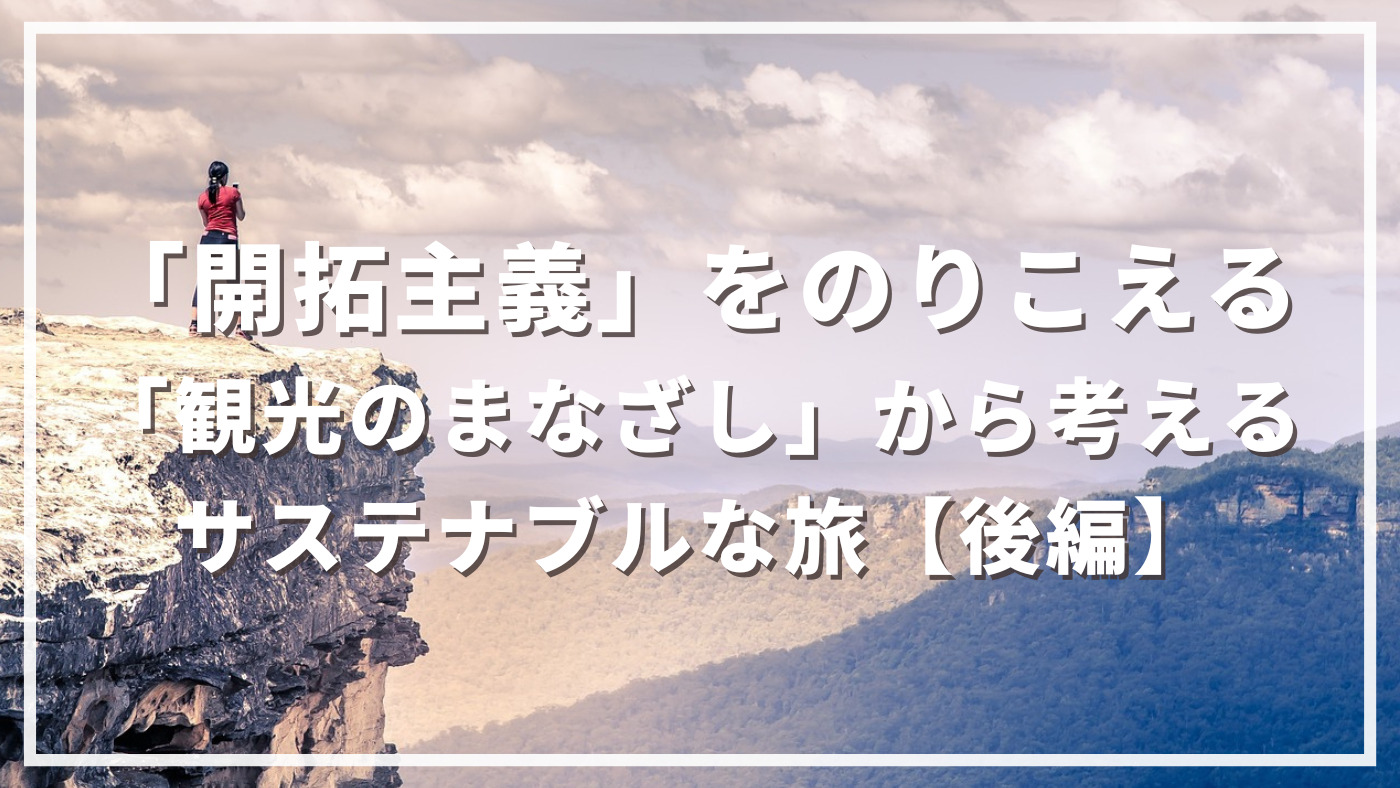
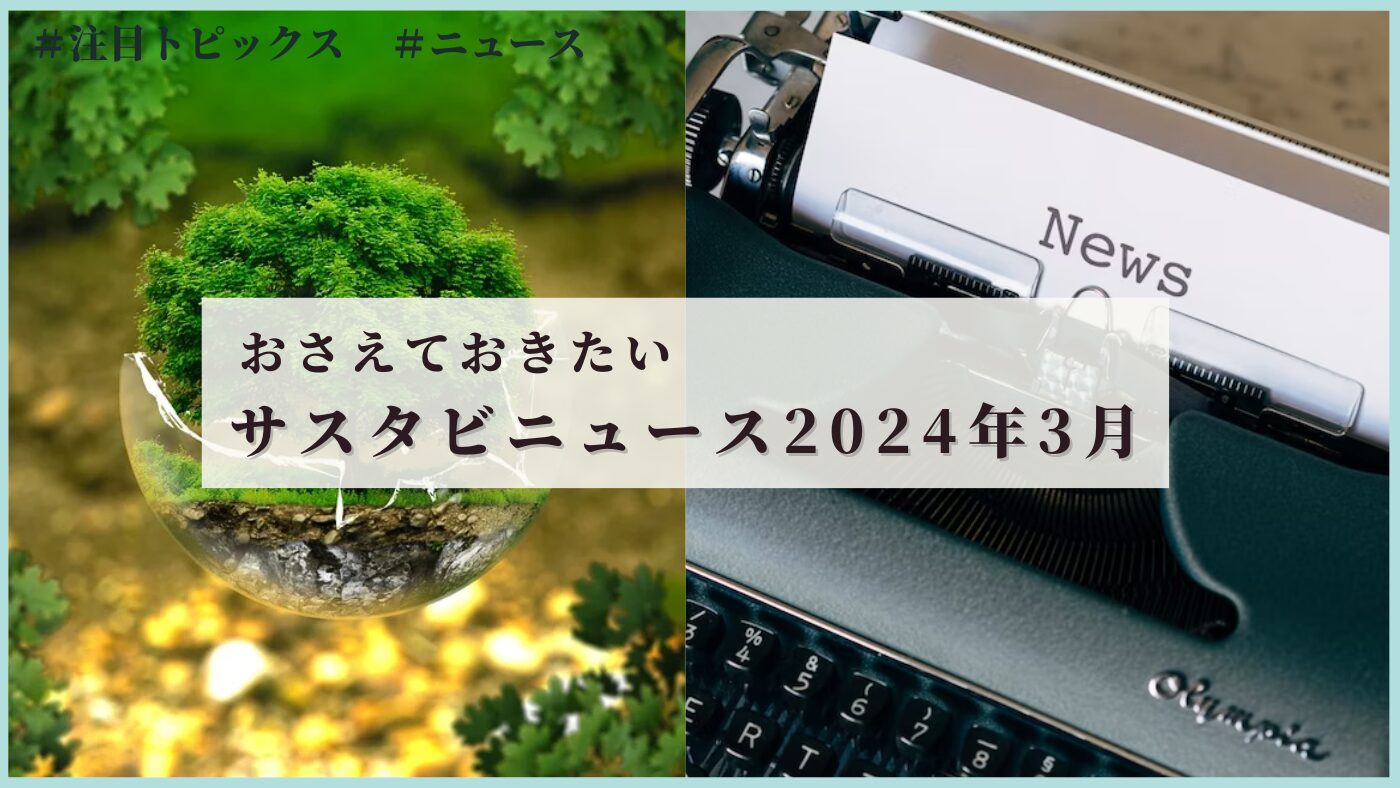

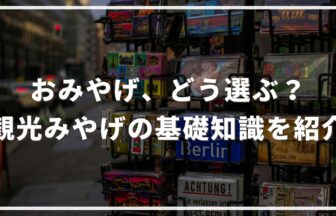
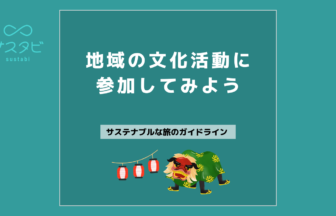
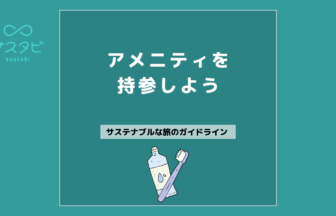




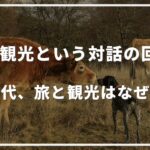




-150x150.jpg)





この記事へのコメントはありません。